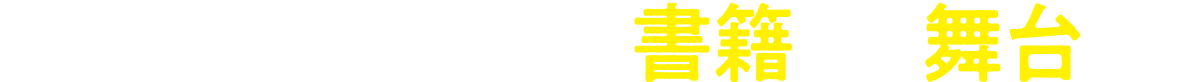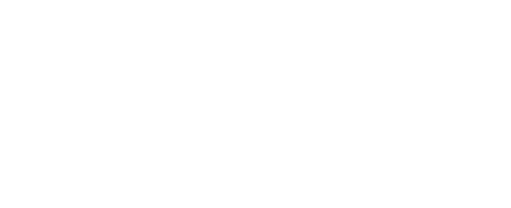書式設定
- 文字サイズ
-
- 小
- 中
- 大
- 特大
- 背景色
-
- 白
- 生成り
- フォント
-
- 明朝
- ゴシック
- 組み方向
-
- 横組み
- 縦組み
書式設定
「第7回」
6
地下鉄東山線名古屋駅の改札前で、とある中学生の男女が初めてのデートの待ち合わせをしていた。
ふたりとも、異性とのデートは初めてだった。
ふたりとも、
(楽しくないって思われたら、次のデートは無いよね……)
という心配をしていた。
ふたりとも、自分のことを、話のつまらないルックスもパッとしないダサめで退屈めな人間だと思っていた。
女の子の方が、先に待ち合わせ場所に着いた。20分も前だった。
着いてすぐ、見慣れた改札前が、いつもよりずっと華やかなことに驚いた。何が違うのだろう。わからない。でも明らかに何かが違う。初デートで私はそこまで舞い上がっているのだろうか。と、改札の向こうから、男の子も現れた。約束の時間まで、まだ20分もあるのに。まさか、同じ電車だったのか。男の子は、女の子が既に到着していることに驚き、その驚きのせいか、「やあ」も「早いね」も、「お待たせ」もなく、彼女から目を逸らしてモジモジとした。女の子は女の子で、なんとなく、最初の第一声は彼に話してほしくて、やはりモジモジと黙っていた。
数秒の後、男の子は言った。
「どまつりのポスター、すごいね」
「え?」
女の子は顔を上げ、辺りを見回す。そうか。そういうことか。見慣れた改札前がいつもよりずっと華やかだったのは、どまつりのカラフルでレトロポップなポスターが、 地下空間全体をジャックしていたからだった。ポスター掲示用のすべての場所が、どまつりになっている。
「どまつり、良いよね。私、好きなんだ」
女の子は言った。
「じゃあ、行く?」
男の子が言った。
「今年のどまつりは、一緒に行く?」
「え? 良いの?」
「え? だめ?」
「ううん。全然。行く。一緒に」
今日のデートで振られるかもしれないと心配していたのに、そのデートをする前から、次のデートの約束が出来てしまった。
「あ、そういえばさ。名鉄の前にあるナナちゃん人形、どまつりバージョンになってるらしいよ。ちょっと見ていかない?」
そう言って、男の子が歩き出す。
(ありがとう、どまつり)
女の子は心の中で呟いた。
久屋大通公園のエディオン久屋広場では、ひとりのホームレスが、色あせたタオルを畳み、垢じみた衣類を畳み、数少ない私物の小物と共に紙袋に詰めていた。そして、 その作業を終えると、今度は自分の段ボールハウスを丁寧に解体し始めた。
「あんた、引っ越しするのか?」
隣りのホームレスが声をかけてくる。
「もうすぐ、どまつりだからな」
「あー、今年もそろそろか。早いな」
「おまえは移動しないのか? ミズベヒロバのゴジラだって、引っ越しを済ませてるぜ」
「あんなでっかいゴジラが? いや、それは気づかなかったな」
「テレビ塔の下に行ってみろ。ゴジラのやつ、今はそこでくつろいでる」
「ふーん」
隣人は知っていた。
この男は、どまつりの会場設営の邪魔にならないよう、毎年最初に引っ越しをしていく。そして、どこかの公園の水道で髪を洗い、器用に自分一人でハサミで散髪し、一年かけて貯めたへそくりでユニクロのパンツとポロシャツを買い、予選から毎日どまつりのステージを客として楽しむのだ。
(別れた家族の誰かが出場してるのかもしれないな。息子とか。娘とか)
そんな風に彼は想像しているけれど、本人に質問したことはない。そんなヤボなことは訊かない。
「じゃ、俺も準備をするかな」
寝慣れた場所から移動するのは不便だったが、隣人もまた、自分を名古屋人だと思っていた。
(一年に一度くらい、名古屋に貢献するのも悪くない)
そう呟きながら、彼も、衣類を畳み始めた。
坂井優奈は、中部国際空港の職員だ。中部国際空港、通称「セントレア」。優奈がそこで働き始めて今年で7年になる。主な担当は、貨物輸送機から荷物を受け取る貨物センター業務だ。
「これ、同じ段ボールが47個もあるんですけど、差出人、何て読むんですかね」
新人社員の村瀬龍也が、優奈に尋ねてきた。
「宙嵩」
そう、角角がくっきりとした筆跡で書かれている。
「そらね」
「そらね?」
「新千歳空港からの荷物でしょう? それ、北海道から来るどまつりチームの荷物よ」
「へえー。どまつりって、北海道からも来るんですか?」
「海外からだって来るよ」
「へえー、そうなんだ。でも、どまつりって客は見てるだけなんでしょ?」
「ん?」
「俺、出身が徳島で、ずっと阿波踊り踊ってたから、見るだけってのはどうも燃えないっていうか」
その言葉を聞いて、優奈は作業の手を止めた。パンパンとパンツの埃を手で払うと、
「龍也くーん。君はまだまだ名古屋は素人だね」
と言ってニヤリと笑った。
「どまつりも、客は一緒に踊るよ。ファイナル・ステージのラストには、総踊りってやつがあるからね」
「総踊り? どまつりに総踊りがあるんですか!」
龍也の徳島人としての血がカッと上昇した。
「なら俺、今年は有休取ってどまつり行きます!」
龍也はそう高らかに宣言をした。
「や、ごめん。それは無理」
優奈が即座に却下する。
「え? 無理? なんでですか?」
龍也の質問に、優奈は軽く肩をすくめた。
「その日はもう私が有休を取ってるから」
「え……」
祭りの日が近くなるにつれ、ゆっくりと、だが、確実に、街の人の気持ちも祭りにフォーカスしていく。
深く関わる人にも、当日だけ楽しむ人にも、参加はせず、ただその日の街の混雑にびっくりしただけの人にも、祭りは何かを残していく。とてもポジティブな何かを。暖かい何かを。
だが、その年、名古屋の人々はまだ知らなかった。
祭りの中止の決定が、すぐそこまで迫っていることを。
7
名古屋市中区栄4-16-33。公益財団法人にっぽんど真ん中祭り文化財団は、そこに建つ日経ビルの2階にある。大夏たちが呼ばれたのは、そのワン・フロア上。3階の大会議室だった。
整然と並んだ長机。前方左側の席にはお揃いの真っ赤なスタッフTシャツを着た学生委員たちが固まって座っている。他は、今年のどまつりに出場予定のチームの代表たち。各チーム数人ずつで固まり、不安げな表情でボソボソと小声の私語をしている。大夏は、松葉杖移動だったせいで到着が遅く、説明を受ける側としては最後の入場者だったようだ。空き席は最前列の真ん中にしか既になく、なので大夏は仕方なくそこに座った。やがて、スーツ姿の男性が三人、入ってきた。先頭は、オーディション時にも見た長身の男性。文化財団の専務理事である水野孝一だ。その後ろの二人を見て、大夏は「うぐ」と変な声を出してしまった。大夏が、今でも時々夢に見る男たちだった。
緒賀冬巳。その相棒の鶴松祐希。二人とも、愛知県警の刑事だ。
今年の春、コメダ珈琲栄四丁目店の目の前で、大夏は緒賀から強烈な突きをお見舞いされた。鳩尾にめり込んだ拳。文字通りの悶絶。意識が絶えるほどの悶えというものがどういうものか、大夏はあの時、自らの身体で思い知った。それだけではない。その翌日の夜、大夏は中警察署の取調室でまたも緒賀と再会した。緒賀は大夏の頭髪をいきなり鷲掴みして、
「おまえを十年はブタ箱にブチ込んでやるからな!」
と凄んだ。相棒の鶴松はその暴力行為を隣りで容認しただけでなく、
「しかしあれだね。君、緒賀さんのパンチを受けて無事にまだ生きてるってすごいね」
と、ヘラヘラと笑っていた。あの笑顔にも傷付いた。
「皆さん。どまつり本番に向けての練習、お疲れ様です。皆さんの日々の努力、本当に素晴らしいと思っております」
正面中央に立つやいなや、水野はすぐに話し始めた。
「そんな中、本日、極めて残念なお報せを皆さんにしなければならないこと、私自身、非常に無念に思っております」
会議室全体が、ざわりとする。
緒賀が一歩前に出た。
「皆さま、初めまして。愛知県警の緒賀と申します」
「同じく、愛知県警の鶴松です」
後ろめのポジションをキープしたまま、鶴松も簡単な自己紹介をする。
「実は今、名古屋市内で連続傷害事件が発生しています。被害者は、現在判明しているだけで5名。最初は全治数日程度の軽傷でしたが、犯行は毎回エスカレートしており、5件目の被害者は全治一ヶ月を超える重傷を負いました」
言いながら、緒賀がチラリと最前列の大夏を見た。
(重傷のくせに、なぜおまえはそこにいるんだ?)
とその目が言っている。大夏は、自分の尻と足のギプスを触りながら目線を落とした。
「被害者は、全員、今年のどまつりに出場予定の方でした」
また、会議室全体が、ざわりとする。
「これからお話しすることは、くれぐれも内密にお願いします。SNSに書き込んだり、マスコミに勝手に話をしたりしないよう、厳にお願い申し上げます」
言いながら緒賀は、胸ポケットから折りたたんだコピー用紙を取り出し、それを開いて会議室全体に見せるよう、自分の顔の上に掲げた。
「本日、どまつり実行委員会宛に、脅迫状が届きました。これはコピーですが……実はこれ、二通目の脅迫状になります」
緒賀は、言いながら、ひとりひとりの表情を確認するかのように、ゆっくりとその場にいる全員を見回す。もしこの中に犯人がいるなら、自分はそれを見抜く眼力があるのだぞ……そう言いたそうにも見えた。確かに、もし自分が犯人だったら、恐怖で表情は強張り目も逸らすだろう。そんなことを大夏は思う。
「繰り返しになりますが、このことについてはくれぐれも内密にお願いしますね。SNSに書き込んだり、マスコミに勝手に話をしたりしないように。では、読みます」
そして緒賀は、低いがよく通る声で、二通目の脅迫状を読み上げた。
『にっぽんど真ん中祭りの実行委員会に告ぐ。私は、ど祭りと、ど祭りに関わるすべての人間を深く憎む者である。今年のど祭りを中止せよ。あるいは、現金で、10億円を支払え。さもなくば、次は、人が死ぬぞ』
専務の水野が、ハンカチで自分の額に浮かんだ汗をそっと叩く。会議室のクーラーはかなり強めに設定されているのに。と、大夏は急に、脅迫状の「次は」という単語の持つ意味に慄然とした。
次は、人が死ぬ……次は、殺人事件……傷害の度合いを5件連続でエスカレートさせてきて、次からはついに殺人事件……5件目の被害者は自分。ということは、ひとつ順番がずれていたら……俺は殺されていた!
俺が、殺人事件の被害者になるところだった!
階段に潜んでいたあの男。手にしていた刃物。記憶とともに大夏の胃はギュッとなり、尻と足の怪我がズキリと痛んだ。
(マジか……ギリギリじゃないか……怖え……)
緒賀は、脅迫状を読むと、しばらく黙った。大夏側に座る会議室の全員も黙っていた。専務の水野が、また額の汗を拭き、空咳を2度した。それから、ようやく話を前に進めた。
「まず、その、これは当たり前のことですが、不審者には厳重に注意してください。この会議後、捜査本部への直通電話番号を皆さんにもお渡ししますので、チームのお仲間と共有してください。そして、少しでも不審な者を見かけたら、あるいは何か周囲に違和感を感じたら、すぐに警察へ連絡してください。結果、ただの勘違いであっても何も気にすることはありません。何かあってからでは遅いのです。少しでも気になることがあったら、捜査本部まで電話をして下さい。これはとても大事なことです」
聞きながら、大夏は小さく頷く。最前列に座っているせいで、背後のみんながどんな表情なのかは確認出来ない。
「私は、どまつりを愛しておりますが、どのようなエンターテイメントも、人命に勝るものではありません」
水野の声が、大きくなった。大夏の両側に座るダンサーたちが、皆、少し身じろぎをしたのを大夏は感じた。
「現実に、被害者が出ていること。犯行がエスカレートしていること。そして、犯人逮捕の目処が現在まだ立っていないこと。それらを総合的に考えると、私としては、大変……大変、無念ではありますが……今年のどまつりは中止も真剣に検討」
水野は、その言葉を最後まで言うことが出来なかった。
「中止は絶対にダメです!」
ガタンと大きな音を立てて学生委員の女の子がひとり立ち上がった。体をひねって彼女を見る。大夏も顔を覚えている女の子。委員長だ。今年のどまつりの学生委員長。名前は、確か、稲熊彩華サン。
「中止なんてあり得ないです!。なんで、簡単に諦めるんですか?」
彼女は、怒りで顔面が蒼白だった。
「簡単に考えてなんかいない! でも、何かあってからでは遅いんだ!」
水野の声にも少し怒気が含まれたように大夏は感じた。が、学生委員長は怯まなかった。
「私、毎年実行委員やってたから知ってます。去年だって一昨年だって、公表してないだけで、脅迫状みたいなの、たくさん来てましたよね? テロを起こすとか、参加者殺すとか、そういうの、たくさん来てましたよね?」
「それらは、ただのイタズラです。でも、今年は、実際に怪我をした人たちが出てるんです」
「だからって中止ですか? そうやって、卑劣な犯人に成功体験を与えて良いんですか?」
「しかし」
学生委員長は、反論しようとする水野の言葉に、猛然と自分の思いを被せた。
「だったら、来年からは、日本中のすべてのお祭りを中止にしますか? こっちが下手に出たら、あいつら、調子に乗りますよ? 匿名で脅迫状出したり、ネットに犯行予告書き込んだり、そういう卑怯な連中が、みんなみんな飛び上がって喜びますよ? エスカレートしますよ? あいつら、自分が頑張れないから、頑張ることを楽しめないから、他の人たちが頑張ることを邪魔するんです。そんなやつらに、今年のどまつりは負けるんですか? 成功体験を与えるんですか? どまつりが負けたら、次はどうなるんですか? 祇園祭ですか? ねぶた祭りですか? 徳島の阿波踊りですか? そうやって歴史あるお祭りを全部全部中止にして、日本はそれで良いんですか?『人命第一だもん良かった良かった』ってなるんですか?」
言うほどに、話すほどに彼女は怒りが抑えきれなくなり、最後は自らの足をドンッと床で踏み鳴らした。
「……私は、納得いきません。中止だけは、絶対に、認めないです……」
彼女はそう発言を締めくくると、右手でゴシゴシと顔をこすり、机の上の黒いリュックをつかんで会議室から出て行った。その横顔には、涙が光っていた。彼女が後ろ手でドアを閉めた数秒後、彼女の隣に座っていた学生委員が手を挙げた。すらりと背の高い女性だった。水野は彼女に(どうぞ)と言うように右手を差し出した。その子は小さく頷き立ち上がった。
「どまつりМC班の班長、杉下奈緒です。あの……中止はまだ『検討』ってだけで、『決定』ではないんですよね? たとえばなんですけど、どまつりの本番までは、小学校の集団登校みたいに練習の行き帰りも全員で固まって行動するとか、練習場所に防犯カメラ付けるとか、チームごとに警備のボランティアを募集するとか、まだまだやれることってあるんじゃないでしょうか? そうやって、これ以上被害者を出さないようにしている間に、刑事さんたちが犯人捕まえてくれれば、どまつりも映画も、無事にそのままやれるってことになりませんか?」
「……」
「どまつり開幕まで、あとたったの四日です。ファイナルのステージまで、あとたったの六日です。たったの六日間なら、私たちの努力で、犯人に負けないことも可能じゃないでしょうか?」
会議室の後方から、
「賛成します!」
「そう思います!」
「もう1週間もないんです!」
「みんなで力を合わせて乗り切りましょう!」
などの声が飛んできた。
「中止は負けと一緒です!」
「負けたくないです!」
「一年間、みんなで頑張ってきたんです! いろんなことを犠牲にして、頑張ってきたんです!」
会議室は騒然となった。
8
美桜は、「甍」の厨房で玉ねぎスープを作っていた。皮を剥いただけの玉ねぎをコンソメでコトコトと煮て、仕上げに黒コショウをふるだけのスープ。元の玉ねぎが素晴らしいので、それ以上の何かをする必要性を美桜はまったく感じない。
と、
「うわー、香り最高!」
そう言いながら、みさきが顔を出した。生成りの無地のTシャツに、黒のダメージ・ジーンズ。グレイスでの艶やかな着物姿のチーママとはまるで別人である。四人掛けの店のテーブルの上には、みさきへのお裾分け用に、既に段ボール箱がひとつ用意してある。みさきは、中から玉ねぎをひとつ手に取り、
「硬く締まってて重みもあるし、今年も良い玉ねぎねー! 毎年ありがとう、美桜ちゃん」
と、それに頬擦りしながらお礼を言った。
「毎年40㎏来ますからね。お店を営業してた時ならともかく、今だと私と母では絶対食べきれなくて。貰ってもらえて、こっちこそ助かってます」
「で、相変わらず、差出人は不明なの?」
「ええ、まあ」
「案外、望月先生からだったりして」
「それは無いです。望月先生がお店に来るより前から届いてるんで」
「あらあ。望月先生より熱心なファンってことかしら。美桜ちゃんの」
美桜は、柳ヶ瀬のグレイスに来る前は、名古屋の錦で働いていた。そしてそこでも、 売り上げナンバーワン・ホステスだった。みさきはそのことを言っているのだ。
「いやいや。違うでしょう。それならお客さんはここじゃなくて錦のお店に持ってきたはずだし。ま、良いんです。確かに最初は不気味だったけど、母が『きっと甍のファンからよ!』って言って毎年大喜びするので、遠慮なくいただくことに決めたんです」
言いながら、美桜ももう一度その段ボール箱を見る。
「玉ねぎ生産量日本一」「北見玉ねぎ」
そう特大の文字で印字されている。つまり、北海道の北見市からこの玉ねぎは送られている。ちなみに、美桜の知人に北海道人はいない。誰なのだろう。そして、なぜ、玉ねぎなのだろう。
過去、何度も考えた疑問。しかし、それを考え続けることは出来なかった。テーブルの上に置いておいた美桜の携帯が鳴ったからだ。
☆
どまつり学生委員長である稲熊彩華は、火にかけられたまま透明な鍋蓋をかぶせられたような暑さの街を、汗だくになりながら足早に歩いていた。
久屋大通公園のエディオン久屋広場。両側を青々とした樹木に挟まれて気持ちの良い空間。そして、三日後には、どまつりのファイナル・ステージが出現する場所。既に、ステージ・セットを組むための資材は積み上げられている。櫓型に重なり合った鉄パイプ。ステージ用の大型パネル。それらを覆うブルーシートが、陽射しを眩しく反射している。
『にっぽんど真ん中祭りの実行委員会に告ぐ。私は、ど祭りと、ど祭りに関わるすべての人間を深く憎む者である』
刑事が読み上げた脅迫状のことを考える。
意味がわからない。
どまつりを深く憎むって……そんなことがあるだろうか。たとえば、最高のパフォーマンスをしたと思ったのにファイナルに残れなかったとか、そういうことはあるかもしれない。練習や本番で怪我をしてしまったとか、そういうこともあるかもしれない。でも、それって、殺人事件を起こすほどの憎しみに繋がるものだろうか。
それとも、憎しみ云々は実は嘘で、単にお金が欲しいだけ?
それともそれとも、大勢の人が楽しんでるものを壊したいっていう、単なる愉快犯のクソ野郎?
と、彩華の携帯がブルブルと震えた。委員会仲間の奈緒や和樹からだろうか。一応、ポケットから取り出して、通知のバナーを確認する。相手は、ムーン・ライズという芸能プロダクションのマネージャーだった。どまつりは、学生委員長と名古屋のご当地タレントの二人で司会をするのが通例だったが、年々祭りの規模が拡大し、テレビ中継なども入るようになった関係で、今年からは、バック・ステージ中継のリポーターもキャスティングすることになったのだ。そして、その初代として採用されたのが、どまつり大好き声優として売り込みのあった栗生凜さん。ムーン・ライズ社は、彼女が所属している事務所である。
(もう、中止の連絡が行ったのだろうか)
そう考えただけで、彩華は道路の上に座り込みたくなる。
「私、親友が愛知県の出身で、それで、どまつり、5年連続観ていて、そのうち、親友より私の方がどまつりの大ファンになっちゃって。なので、今回のリポーター募集のお話を聞いた時、アニメのレギュラーより、どまつりのスケジュールの方を応援して欲しいって、私、事務所に頼んだんです」
先月に一度顔合わせをした時、栗生凛は、そう言って、本当に嬉しそうに微笑んだ。彩華は恐縮して、何度も何度も、年齢は一つしか変わらないこのアイドル声優の女の子に頭を下げた。どまつり中止と知ったら、彼女もさぞがっかりすることだろう。
出る。
「もしもし」
「稲熊さん、お忙しいところ、直接お電話しちゃってすみません。実は、当日の控え室についていくつかお伺いしたいことがありまして」
「え? 控え室?」
「はい。控え室、ステージ裏に仮設されるプレハブなんですよね。そこ、姿見の鏡は置いてありますか?」
「鏡?」
「はい。もしあるようでしたら、その鏡の大きさも教えていただきたくて。もし小さいものしか無いようでしたら、東京から持っていくことも考えたいなと」
「え? 東京からわざわざですか?」
「はい。栗生が、憧れのどまつりに出るのだから、自分にやれることは完璧にやりたいと言っていまして」
「……」
「? もしもし?」
「あ、すみません。ちょっと感動してしまって」
「え?」
「あの。鏡はあったと思いますが、サイズまではここに資料が無いので、調べて春川さんにショートメールします。それで大丈夫ですか?」
「助かります。ありがとうございます」
切れる。
事件のこと。中止の可能性が高いこと。まだ伝わっていないようだ。もちろん、時間の問題であることは間違いない。
短い電話だったが、彩華の心には新たなダメージがあった。そして、猛烈に喉が渇いてきた。
☆
着信画面に「弟」と一文字だけの表示。以前は「クソボケ」で 登録していたのだが、それを知った母の琴子から、
「お願いだから変えて! 普通にして!」
と泣いて頼まれたのだった。ちなみに、変更したらすぐにケロッとしたので、あの時の母は嘘泣きではなかったかと美桜は今も疑っている。
「美桜ちゃん、出ないの?」
みさきが言う。
「弟さんでしょう? 姉弟で仲良くするのも親孝行の一つよ」
みさきは更にそんなことを言う。美桜は、しぶしぶ電話に出た。
「姉ちゃん、俺だよ! 俺、俺! 実はさ、メリッサとレイチェルと一緒に映画に出ることになったんだけど、実は実は困ったことになっちゃって、本当は家族にも話しちゃいけないって言われてるんだけど」
美桜は電話を切った。
「え? 何で切ったの!? まだお話し途中だったじゃない?」
「や、オレオレ詐欺かと思って」
「そんなわけないじゃない。メリッサさんとレイチェルさんの名前も出てたし、それに何かに困ってるって」
「でも、声を聞いた瞬間に、こいつを殴りたいって気持ちがお腹の底からぶわぶわぶわって」
美桜の言葉を聞いて、みさきは大きくため息をついた。と、再び美桜の携帯電話が鳴った。
着信画面に「弟」と一文字だけの表示。
「出てあげよう? 美桜ちゃんももう大人なんだから」
そう言って、みさきは美桜を見つめる。美桜は、電話に出た。
「だからさ、姉ちゃん! 犯人を捕まえないことにはメリッサやレイチェルがメッチャ困るんだよ、あ、それに、小料理屋の雪乃さんもキャバ嬢のゆめちゃんも、女子大小路の名探偵である俺のことを信じるって。何なら、少しなら探偵料も払うからって」
美桜は電話を切った。そして、みさきが何か言うより早く、
「さっきより3秒は我慢しました」
と言った。
「嘘。さっきよりも短かった」
みさきが睨む。
「え? 本当ですか?」
「うん。短かった」
「……でも、みさきさん。あいつは、生まれついてのクソですよ?」
そこで、三度めの電話が鳴った。だが今度は、美桜の携帯ではなかった。厨房と、かつての喫茶「甍」のフロアを仕切っているカウンターの上の固定電話が鳴っていた。この電話が鳴ることは滅多に無い。もう何年も鳴っていない。今、喫茶「甍」の店の電話番号を知っている人間なんて、日本に十人もいないのではないか。
なので、これも大夏だ。携帯を二度切られ、次はもう出てもらえないと思い、発信者がわからない店の黒電話にかけてきたのだ。いつの間に、そういうくだらない知恵を付けたのだろう。
そもそも、美桜はこの旧式のFAX付き電話が嫌いだった。捨てたいと思っていた。琴子が猛反対しなければ、本当に捨てただろう。なぜならこの電話は、美桜に、父の最後の声を再生した電話だからだ。
19年前の夏の日。まだ営業していた「甍」。オンフック機能で店中に響き渡った父の声。
「お父さん、フィリピン・パブの女性を好きになってしまったんだ。これから、彼女と駆け落ちをする。だから、琴子、美桜、大夏……みんな、父さんのことは忘れてくれ。ごめん。じゃ」
その電話を、今、大夏が鳴らしている。そう思うと、美桜は、大夏のことがまた少し嫌いになった。
怒りを胸に溜めたまま、美桜は固定電話のオンフック・ボタンを押した。大夏のためだと、腕を顔まで持ち上げる動作すら嫌だったからだ。
が、違った。その電話は大夏からではなかった。聞き覚えのない女だった。その女は、いきなりこう言った。
「あの男に、気をつけて」
「は?」
「志村椎坐に、気をつけて」
「? 志村?」
☆
10分後。
彩華はよく知らない居酒屋のテーブルに座っていた。陽に焼けて色褪せた紺色の暖簾。天井からぶら下がっているのは燻んだ白熱球。壁にベタベタと貼られた手書きのメニュー。四人掛けのテーブル席が縦に五つ並んでいて、そのうちの一つに彩華はひとりで座る。明るいうちから飲める店ならばどこでも良かった。そして、ひとりで居酒屋に入るのも、明るい時間から飲み始めるのも、彩華には初めてのことだった。
油でべとつくメニューを開くと、店員が来た。
「年齢確認、先にいいっすか?」
無言で財布を取り出し、そこから学生証を引っ張り出す。
「ご協力どーもです。では、ご注文を」
生ビールとどて煮と手羽先をオーダーする。生ビールは特大ジョッキで。店員が去る。思考はまた、今日のあの会議に戻る。刑事が読み上げた、あの脅迫状。
『にっぽんど真ん中祭りの実行委員会に告ぐ。私は、ど祭りと、ど祭りに関わるすべての人間を深く憎む者である』
ふざけんな。私がおまえを殺してやる。心の中で、彩華は犯人に対して毒づく。おまえのせいで、どまつりが中止になったら、その時は、何年かけてもおまえを見つけ出して殺してやる。それも、とびっきり惨たらしい方法で!
生ビールはすぐに運ばれてきた。特大ジョッキを両手で持ち、彩華は豪快に喉に流し込んだ。
そして、40分後。
「お客さん、大丈夫ですか?」
店員に背中を叩かれ、彩華は起きた。四人掛けテーブルに突っ伏して、彼女は眠っていた。どまつりの準備の追い込みで、この一ヶ月、平均睡眠時間は3時間くらい。ロング・スリーパーである彩華にとっては、体力的にきつい日々だった。そこに、立て続けに特大ジョッキで酒を流し込んだ。生ビールの次はレモン・サワー。その次はグレープフルーツ・サワー。その辺りで記憶が途切れている。
「すみません……大丈夫です……」
言いながら、彩華はのろのろと立ち上がり、トイレに向かった。手洗い場の鏡に映る自分の顔を見る。酷い顔だ。悲しい。こんな顔を他人に見られるのは耐えられない。もう家に帰って寝てしまおう。そう彩華は決意する。蛇口をひねり、顔を洗い、外に出てすぐに会計をお願いする。2780円を支払って店を出る。安いとは思うが、それでも、バイトを休んでどまつりの準備に集中していた彩華には痛い出費だった。
歩く。
未だ、外は容赦のない暑さだった。 先程の居酒屋が空調「強冷」だった反動で、彩華は体全体が漬物石になったかのようなダメージを感じた。
でも、歩く。他に選択肢が無い。
歩道の石畳につまづき、時々、電柱に手をついて休んだりしながら、彩華は西川端通のアパートまで歩いた。
周りを植栽にぐるりと囲まれた、築50年越えの二階建て木造アパート。外階段脇のポストには、乱暴に突っ込まれた大量のチラシとダイレクトメールが溜まっている。中には必要な郵便物もあるのかもしれないが、パッと見では判別できない。彩華はそれらを全部引っ張り出し、くしゃくしゃのまま鞄に押し込んだ。錆が浮いた手すりを気にせず掴み、階段をなんとか上る。途中、一階の部屋の電気がすべて消えていることに気づく。あのパワハラ大家は留守らしい。このアパートは、元々は立派な一軒家だったのだが、十年以上前に、二階部分を改築して賃貸アパートにしたという。大家はそのまま一階に住み、二階は彩華のような貧乏学生が三組住んでいる。彩華以外の学生は、今は二人とも帰省中だ。簡単にピッキング出来そうな古いシリンダー・キーを鍵穴に差し込む。回す。ドアを開ける。荷物を投げ捨てながら、部屋の奥に転がり込む。ここで、彩華の体力は尽きた。畳敷きの6畳間に大の字になり、左手でクーラーのリモコンをなんとか掴む。
運転。
風が届き始めると同時に、彩華は浅い眠りに落ちた。どこか遠くで、玄関の呼び鈴が鳴った気がする。どうせ、セールスだろう。どうでも良い。私は眠いんだ。もう起きたくないのだ。だが、なぜだろう。暑い。クーラーが壊れたのか? ものすごく暑い。あと、変なノイズが聞こえる。パチッ……とかパチパチッとか……うるさい。あと、臭い。なんだろう、臭いって。あーもう、眠いのに。私は、すっごく、眠いのに。大家に文句言ってやる。パワハラ・ジジイ大家。あんなショボイ身なりで、名前だけジュリアス・シーザーから取って椎坐とか言うの、滑稽過ぎる。そういえば、あの病院に呼びつけられた一件はなんだったんだろう。あー、本当に暑い。臭い。うるさい。私、すっごく眠いのに!
彩華は薄目を開けてみた。視界が白く煙っている。プラスチックの焦げたような匂いが鼻をつく。
「!」
恐怖が全身を走り、彩華は飛び起きた。異変の原因は彩華からわずか3メートルのところにあった。
彼女の部屋の玄関が、燃えている! それも、轟々と、音を立てて燃えていた。彩華は、つんざくような悲鳴を上げた。
と、その時だった。
彩華の背後の窓ガラスが、突然、派手に砕け散った。
そして、人がひとり、勝手に彩華の部屋に入ってきた。