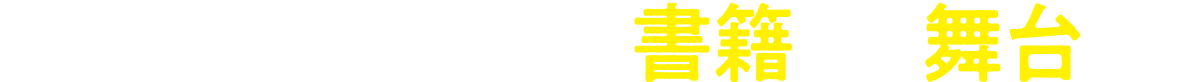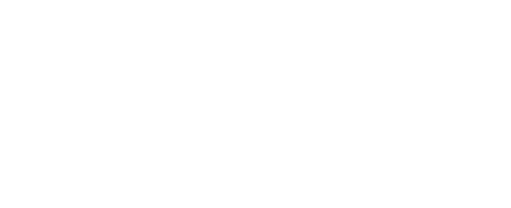書式設定
- 文字サイズ
-
- 小
- 中
- 大
- 特大
- 背景色
-
- 白
- 生成り
- フォント
-
- 明朝
- ゴシック
- 組み方向
-
- 横組み
- 縦組み
書式設定
「第8回」
第三章
1
女の身体を、力づくで引き寄せる。
そして突き飛ばす。
男には、蹴り。
全力で。鳩尾に。その後はベランダだ。
落下する。
数秒後には、骨が砕け、肉が潰れる鈍い音。
ぐしゃり。
それを彼は、暗くて強い夜風に吹かれながら聞いた。
犯罪者になって判ったこと。
それは、月並みでありきたりだが、夜、眠れなくなるということだった。部屋の電気を消すと、あの光景が蘇る。
落下していく男。その驚愕の表情。
骨が砕け、肉が潰れる鈍い音。
いくつか市販の入眠剤を試したが、あまり効果は無かった。ずっと入眠剤を使う金も無かった。結局、最も不眠に効果があったのは「疲労」だった。シンプルに、肉体を疲れさせること。彼は、そういう仕事をすることにした。眠るために。
ある日、滅多に着信の無い彼の携帯電話が震えた。あと5分で昼休憩が終わるという時だった。画面を確認すると、やはりそうだった。
あの女。
あの日、あの時、あの音を同じ場所で聞いた女だった。
目立たぬよう気をつけながら、作業場の外に出る。
「もしもし」
心臓の鼓動が速くなるのを感じながら、彼は電話に出た。
女の話は、今年のどまつりについてだった。
「もう、我慢しなくて良いんじゃないかしら」
そう女は言った。
「こんなチャンス、なかなか無いと思うの」
夜。
小さな台所に、六畳一間の住居。ちゃぶ台と簡易なベッド。どちらも、粗大ゴミに出されていたのを拾ってきたものだ。今日も全力で身体を苛めるように働いたが、眠気はまったく来てくれなかった。
女の言葉について考える。
「もう、我慢しなくて良いんじゃないかしら」
あの光景を思い出す。
落下していく男。その驚愕した顔。
女の言葉について考える。
「こんなチャンス、なかなか無いと思うの」
どまつり。
落ちていく男。
どまつり。
自分も出るはずだった祭り。
どまつり。
ぐしゃり。
一睡も出来ぬままに朝を迎え、彼は仕事に向かう。作業場に入ると、社長が大声で出張希望者を募っていた。
「場所は名古屋の高島屋! 期間は一週間!」
元々予定していた人間が、真夏にインフルエンザにかかって行けなくなったらしい。時期は八月の末。ちょうど、今年のどまつりが開催されるタイミングだ。
なんと言うことだ。
彼は嘆息する。
試されている。
そうも思った。
自分は、今、試されている。陰険な神から、一度決めたことを守り通せるかどうか試されている。
またしても、あの女の声。
「もう、我慢しなくて良いんじゃないかしら」
どうやら、自分は負けるらしい。彼は、雇い主に向かって小さく手を挙げた。
「私、行きたいです」
2
名古屋市中村区のとある角地に立つ12階建てのビル。その6階の個室。
白いブラインドは45度の角度で少し開けられ、その向こうでは、名古屋の空が茜色に染まっていた。部屋の中央には、上品な木目のマホガニー製の両袖机。中央にMacBookが一台とトラックボール・マウス。コーヒーの入ったカップが二つ。書類は一枚も無い。その代わり、という訳ではないが、デスクの両端には、深緑のマントに立体機動装置と双剣を装備したミカサ・アッカーマンの可動フィギュアが、ポーズ違いで二体、置かれている。この個室の主人は、強い女性が好きだった。美しくて、強い女性だ。そのどちらか一つでも欠けてはダメだと、この個室の主人は思っていた。
「い、一千万円ですか?」
来客用の椅子に座る中年女性が悲鳴に近い声を上げた。
「ふ、不倫の場合の慰謝料の相場は、50万円から頑張っても300万円くらいって聞いてますけど……」
痩せた体にベージュのスーツ。悲鳴の次は、消え入りそうな小さな声で女性は言った。
「哀しい現実です。日本の弁護士は、本当に喧嘩が下手だ」
望月康介は、そう言ってからおもむろに、芝居がかった満面の笑みを浮かべた。
「しかし、私、望月康介、肉体的な喧嘩は不得手ですが、法律を駆使した喧嘩なら誰にも負けません。慰謝料は一千万円。あらゆる手を駆使してむしり取りましょう!」
「あらゆる手、ですか?」
「そうです。あらゆる手、です。塀の向こう側に落ちない範囲で、とことん、無慈悲に、グワッとむしり取ってやりましょう!」
言いながら、望月は、力強くむしり取る動作をしてみせる。勢い余ってデスクを少し叩いてしまい、ミカサ・アッカーマンのフィギュアの顔が少し動いた。望月は、それを丁寧に直す。そして、同じくらいの丁寧さでこう締め括った。
「慰謝料も大事ですが、それよりも大切なのは、あなたの誇りです。人権と言っても良い。あなたの夫は、30年間も、あなたに対して嘘と裏切りを積み重ねた。それがどれほど重い罪か、あなたは彼に思い知らせるべきだと思いますよ」
5分後。依頼人は退室した。
「先生。私、夫と戦ってみます」
そう言って、彼女は最後、頭を下げた。
「頑張るので、どうか、よろしくお願いします」
望月は、冷めてしまったコーヒーに口をつける。
(まあ、 20%というところだろうな……)
小さく鼻を鳴らす。20%というのは、彼女が最後まで頑張れる確率のことだ。
(せめて、「戦ってみます」ではなく、「戦います」と言い切って欲しかったな……)
とはいえ、彼女の人生は彼女のものだ。望月の人生ではない。他人の人生に手を差し伸べるのは難しい。弁護士といえど、だ。
MacBookを開く。
スクリーン・セーバーは、広中美桜の写真を集めたスライド・ショーに設定してある。
「グレイス」で撮った写真から、後で美桜だけを切り抜いて拡大したもの。
「グレイス」のチーママのみさきから、プライベートでの美桜とのツーショット写真をこっそりプレゼントしてもらったもの。
ネットから拾ってきたもの。美桜はSNSの類いを一切やっていないが、彼女と一緒に写真を撮った人間は、自慢げにそれをネットにアップする。それと、本人に無許可で撮影されたもの。「スゲェ美人発見!」などのコメント付きである場合が多いが、美人と褒めたからといって盗撮が許される訳ではない。
(訴えたら勝てるぞ、おい)
そんなことを思いながら、いつかの訴訟のために、望月は粛々とこれらの「証拠保全」をするのが日課になっている。
ちなみに、このスライド・ショーに加わった最新の写真は、岐阜池田町のレストラン『桜坂』での写真だ。躍動感あふれるこの写真は、美桜が、店の駐車場で、とあるモラハラ夫に強烈な膝蹴りを叩き込んだその瞬間を望月本人が激写したものだ。控えめに言って、傑作である。もちろん、傑作だからと言って盗撮が許される訳ではない。
(訴えられたら負けるな。うん)
そう思う。
(脈、無いんだろうな)
そんなことも思う。急に、とてつもなく大きな寂しさを感じて、望月は驚いた。大声を上げて泣いてしまいたい。が、ここは職場だ。涙が溢れないよう、グッと上を向く。首周りにたっぷりと付いている脂肪が邪魔だ。それでも上を向く。両手を伸ばし、MacBookを抱き寄せる。このスクリーン・セーバーを美桜本人だったらと想像しながら。
「何してるんですか? 望月先生」
いきなり、ドアの方向から秘書の緒方真紀の声が飛んできた。
「へ?」
慌ててMacBookを元の場所に戻す。
「びっくりしたなあ! ノックしてから入ってよ!」
「ノックならしましたよ?」
「聞こえないノックはノックじゃないよ!」
年齢不詳のこの秘書は、望月の抗議を無視して、彼のデスクの上に領収書を一枚一枚並べ始めた。
「な、何?」
「こちらは、お返しします。今年度はもう『グレイス』の領収証は受け取れません……と経理課からの伝言です」
「え?」
「武士の情けで、3枚だけは接待交際費にしておきました。残りの17枚は自腹でお願いします、とのことです」
それだけ言うと、真紀はくるりと背中を向けて部屋から出ていく。追いかけて彼女の足にすがりつこう。そう思って望月が立ち上がった瞬間、彼の携帯が鳴った。
「ふへっ!?」
あまりの驚きに、腰が抜けた。元の椅子に座りたかったが、うまく肘置きを掴めず、彼は絨毯の床に崩れ落ちた。携帯はまだ鳴っている。出なければ。命懸けで出なければ。彼は机に手を掛け、渾身の力で自らの巨体を持ち上げる。切れないでくれ。手を伸ばす。まだ携帯は鳴っている。なんとかそれを掴み、震える太い指で「通話開始」のスライド操作をする。
「み、美桜ちゃん!」
望月は叫んだ。咆哮した。
「ど、どうしたの? 僕に電話をくれるなんて、は、初めてだよね?」
「お仕事中だということはわかっていたんですけど、みさき姉さんが、名古屋のことなら望月先生に相談すると良いわよって……あ、ごめんなさい、みさき姉さんのせいにしちゃダメですね」
「グレイス」では聞いたことのない、柔らかな声音だった。
「いや、何言ってんの。美桜ちゃんからの電話なら、僕は24時間いつでもウエルカムだよ!」
必死に低音を意識しながら望月は答える。心臓が早鐘のようだ。血圧は160を超えているだろう。このまま自分は死ぬかもしれない。が、こういう死に方ならいつでもウェルカムだ。そう望月は思った。
「ありがとうございます。実は、ちょっと変な電話がかかってきまして」
美桜が申し訳なさそうに言う。
「変な電話?」
美桜は、一呼吸だけ間を空けてから望月に尋ねた。
「先生。志村椎坐という人、ご存知ですか?」
3
「担任の先生が、どまつり?とかいうお祭りに、チームを作って出るぞって。だから、私も練習して、それに出なきゃいけないんです。じゃ、行ってきます」
そう言って、美月はそのまま外に出た。
「気は強いが、あれはイイ女になるな。食べごろになるまであと少し、という感じかな? なあ、ヤマモト」
下卑た笑いを浮かべて、志村はヤマモトに話しかける。ヤマモトはずっと無表情だった。そういうところ、美月と良く似ていると沙知絵は思った。
と、窓の外から3回、クラクションの音が聞こえてきた。3回目の音だけが、挑発するように少し長い。
「なんだ? 俺の車にクラクション鳴らすバカがまだいるのか?」
沙知絵の部屋に来る時はいつも、志村はビルの目の前に違法駐車をする。
「俺の車に駐禁を切る警官は名古屋にはいねえ」
それが志村の口癖だった。
ヤマモトが無表情のまま立ち上がり、窓を開けて下を覗き込んだ。
「ボンネットになんか載ってますね」
ヤマモトが言う。
「俺の車にか?」
「はい。それに、フロントガラスに何か挟まってます。メモですかね。自分、ちょっと見てきます」
ヤマモトは小さく頭を下げ、沙知絵の部屋から出て行った。
「さっきのあれ、冗談ですよね?」
志村とふたりきりになったので、沙知絵は勇気を出して切り出した。
「あん?」
「まさか、あの子のことを、そういう対象としては見ませんよね?」
「なんだおまえ。ヤキモチ焼いてんのか?」
「あの子、まだ中学生ですよ?」
「俺はな。この街で一番守備範囲が広い男だ」
そう嘯いて、志村は意地悪く笑った。
「来る者は拒まず。が、去る者は潰す。あるいは、押し倒す。おまえの娘、俺の金で生活しているくせに、いつも俺にちょっとばかり反抗的だからな。現実ってものを、そのうち教えてやるのも悪くない」
「あなた!」
冷静にと思いつつ、顔色が変わってしまうのを沙知絵は止められなかった。
「おまえもだ」
志村が沙知絵に人差し指を突きつける。
「俺に向かって、女房みたいな口を利くな。俺とおまえは対等じゃねえ。俺は金を払う側。おまえはそれを、這いつくばって拾う側だ」
「……」
これ以上、何か言っても意味は無い。逆に、この男を望まぬ方向にけしかけることになるだろう。
「私、お茶を淹れて来ますね」
この話題はもう切り上げよう。しばらく黙り込んだ後、そう決めて沙知絵は立ち上がった。そのタイミングで、ヤマモトが外から戻って来た。
「ボンネットの上に、これが置いてありました」
ヤマモトは、白木の箱を両手で抱えていた。装飾的な英字でワインの名前が刻印されている。シャトー・ペトリュス。
「本物だとしたら、百万近い値段になりますね。で、これがフロントガラスに挟まってました」
白い封筒と、その中に、三つ折りの便箋。ヤマモトはそれを志村に差し出した。志村の背中越しに、沙知絵もその手紙を覗き込んだ。
『志村組長』
達筆な手書きの文字だった。
『先日、錦のクラブで志村組長をお見かけしました。お声はあえておかけしませんでした。なぜなら、組長はその時、安いお酒をお召し上がりでしたから。私、組長を尊敬しておりましたので、とても悲しく思いました。人前ではせめて、このくらいのお酒を飲んでいただきたく。三河』
最近、栄や錦に進出しようとしている余所者ヤクザと小競り合いが起きている。そう志村が愚痴をこぼすのを沙知絵は聞いたことがあった。確か、三河地方と言っていなかったか? 志村は、手紙を薄笑いを浮かべたままゆっくりと読んだ。それから、ワインのコルクの部分を居間のテーブルに叩きつけた。瓶の上部が砕け散り、ワインの芳醇な香りが、狭い部屋にふわりと満ちた。志村は立ち上がると、ワインのボトルをヤマモトの頭上で傾けた。彼の白いワイシャツがあっという間に赤くなる。まるで血染めだ。ボトルが空になると志村は言った。
「ヤマモト、屈辱だろう? これが今の俺の気持ちだ。わかるか?」
「わかります」
ヤマモトは淡々と答える。
「なら、どうする?」
「……」
「こんなことを親である俺にされて、ヤマモト、おまえならどうする?」
「そうですね……」
ヤマモトは、髪からポタポタと赤い雫を垂らしながら、静かに言った。
「三河の連中は経済ヤクザと聞いています。やつらを潰して、やつらの資産を根こそぎいただくというのはどうでしょう。ざっと、20億円ほどになるかと思います」
「に、20億だと?」
「はい。やり方によっては、もう少し増えるかもしれませんね」
「ってことは、おまえ、まさか……」
ヤマモトが沙知絵を見る。(席を外してください)という意味だと沙知絵は理解した。
「タオル、取ってきますね」
キッチンに行く。すぐには戻らない方が良いだろう。なので、タオルの用意だけでなく、お茶も淹れることにした。茶葉の入った戸棚の下の引き出し。そこには、少し厚みのある白い封筒が入っていた。先ほどの、志村宛の手紙が入っていたのと同じ型の封筒だ。
ちょうど一週間前の昼過ぎ。滅多に鳴らないこの家のインターホンが鳴った。美月は学校の補習で、家には沙知絵しかいなかった。志村が突然来たのだろうか。急いで紅を引き、髪の毛を手で整えてから、玄関に行った。が、そこにいたのは、見知らぬ男だった。黒のスーツをすっきりと着こなした男。40代前半から半ば、という雰囲気だった。
「近所に引っ越して来た三河と申します。今日は、引っ越しのご挨拶にやってきました」
男は、熨斗のかかった箱を手に、道端にいるキャッチセールスのような明るい笑顔で立っていた。
「引っ越しって、このビルじゃないですよね?」
沙知絵は、驚いて訊ねた。沙知絵と美月は、志村の命令でこのビルに住んでいる。占有というやつである。不動産競売物件に居座り続け、落札者に対して極めて割高な立ち退き料を要求する。つまり、沙知絵と美月は、志村のビジネスの手駒だった。そんなビルに、新たに誰かが引っ越してくるとは、考えられなかった。
「このすぐ隣りのマンションです。それで、これはお近づきのしるしです」
男は手にしていた箱を、差し出した。
「それでは、今後ともどうぞよろしくお願い致します」
最後まで、感じの良い笑顔と話し方だった。男が帰ると、沙知絵はすぐに受け取った箱の中身を確認した。ブランド物の花柄のタオルが三本。その上に、白い封筒が置かれていた。中には、一万円札が30枚、入っていた。
沙知絵は、このことを志村に伝えるべきか迷っていた。30万円は高額だ。なんとなく、切り出しにくい気がしていた。三河という名前は尚更だ。部屋で暴れる志村が容易に想像出来た。お湯が沸く。茶葉だけを取り出して、沙知絵はそっと引き出しを閉める。このお金のこと。三河と名乗った男のこと。沙知絵はそれらを志村には伝えないことにした。
ゆっくり数字を10まで数えてから、沙知絵は急須に茶葉とお湯を注いだ。
4
その日、望月康介は冴えていた。
「大切な話は電話ではなく、会って話すことが大事だと思う。ぼくは弁護士として、常にそれをモットーにしている。大切な話であればあるほど、直接会って目を見て話すことが大事なんだ」
そう言って、美桜を納得させたこと。プラス1ポイント。
次に、会う場所を、いつもの岐阜・柳ヶ瀬ではなく、名古屋にしたこと。実家から遠くなればなるほど、男女の関係が前進する可能性は高くなる。プラス2ポイント。
もちろん、自分のオフィスで会ったりはしない。オフィスであったら100%お仕事モードになってしまう。ここは、きちんとレストランを予約したい。それも、人気の高い予約困難店の個室が良い。望月は、東区東桜にある個室高級焼肉店『ヤキニク 旭』に電話をした。
「あ、もしもし。私、山猫法律事務所の望月と申します。支配人、いらっしゃいますか?」
今日の今日で普通は予約など絶対に無理なのだが、望月は、かつて、ここの支配人に無償で法的アドバイスをしてあげたことがある。その時に、「うちの予約が取れない時は、私に直接相談してください」と言ってもらっていた。今がその時だ。そう望月は確信していた。そして、奇跡のように予約は取れた。プラス1ポイント。
もちろん、レストランが最高だからといって、手ぶらで向かうようなことは望月はしない。則武二丁目にある花屋に向かう。
「こんにちは。こちら、岐阜の大野町にある河本バラ園生産の薔薇はありますか?」
知っていて、あえて質問形式で話しかける。
「河本バラ園ですか?」
生産元を指定する客は珍しいのか、店員は、驚いた様な顔をした。
「そうです! 世界で初めて青い薔薇を生み出して、青い薔薇の花言葉を『不可能』から『奇跡は起きる』に変えた、河本純子さんという育種家の方がやっていらっしゃる河本バラ園です。これから会う彼女が、そこの薔薇の大ファンでして」
本当は、美桜の親友である夏芽という女性がそこの大ファンで、美桜自身は「グレイス」で、
「なので、私もちょっと影響されちゃって、にわかファンになってしまって」
と言っていただけなのだが、そういう情報を即座にトイレに行ってメモっておくのが、望月の優秀なところだった。こういう細かな情報をきちんと押さえておくことは、勝負どころで女心に刺さるはずだ。
「河本純子さんの薔薇は今は品切れですが、娘さんの麻記子さんが、ぎふ国際ローズコンテストで金賞を取られた『アンヌ』がありますよ」
アンヌは、河本麻記子さんが手がけるローズ・ドゥ・メルスリーというシリーズの新しい品種で、同じ房から淡いアプリコット・イエローやクリーム色、時にはピンクに近い色などの幅広い色合いの花が玄妙に混じり合う、高貴かつ美しい薔薇である。美桜は「量」に心を動かされないタイプと知っているので、あえて小ぶりで上品な花束にしてもらう。プラス1ポイント。
準備万端。あとは「志村椎坐」という男について調べるだけだった。ネットでもある程度の情報は出てきたが、実は、望月の勤める「山猫法律事務所」のデータベースで、「志村椎坐」という名前は山ほどヒットした。「志村椎坐」は、三河派と呼ばれる新興ヤクザとの抗争に破れて引退するまで、「山猫法律事務所」の顧客だったのである。
☆
「匿名の電話があったんです」
焼肉店の個室に入るなり、メニューも見ずに美桜は話し始めた。
「志村椎坐はヤクザの大親分だよ。前に僕たちが酷い目にあったあの男、そう、ヤマモト! あいつは元々志村の子分だったんだ。あんなクソヤローの親分なんだから、それはもう最悪なやつに違いないよ。僕は会ったことないけど」
「ヤマモト? あー、あの人」
美桜のリアクションは、望月の予想の100分の1ほどしかなかった。
「あの人は悪人ですけど、私の敵じゃないですよね?」
「ど、どうしてそんなことがわかるの?」
「わかるのって……あの人とは直接会って話をしたじゃないですか」
「……」
殺人事件が起きてもおかしくないような、山奥の夜のトンネルでのあの事件のことを、美桜はカフェでお茶をしたくらいのテンションで話した。
(やっぱり美桜ちゃんは並の女性じゃないな……)
そう望月は、美桜への憧憬の念を更に強くした。
「で、話をその志村って人に戻しますけど、引退してるヤクザなら、どうして私、志村椎坐に気をつけなきゃならないんですかね」
「それは……そうだね。なんでなんだろう。電話の声は、若い女性だったの?」
「はい」
「そっかー。や、もし電話が男からだったのなら、単にそいつが美桜ちゃんを狙ってるだけってこともあり得るからね。美桜ちゃんに近づきたいから志村の名前を使ってハッタリを利かせた、みたいな? それか、美桜ちゃんを驚かせて反応を楽しむみたいな?」
「なんですか、それ。有り得ませんよ。でね、先生。私、こういうこと、引っかかったままでいるの、嫌いなんですよ。なんでもすぐに白黒はっきりさせたくなる性格なんで」
「あ、うん。それは知ってる」
「で。ここからが本題のお願いなんですけど、先生、その志村って人の住所、調べることはできますか?」
「へ?」
思わず間抜けな声が出た。
「志村の住所? それを知ってどうするつもり?」
「会ってみようかと思って。その志村って人に。目を見て話せば、だいたいのことはわかりますよね。どんな人か、とか、敵か味方か、とか」
「ほへ?」
更に間抜けな声が出た。
「美桜ちゃん、ぼくの話、聞いてた? 志村はヤクザだよ? それも、めっちゃ危険な大物ヤクザだよ?」
「でも、先生、今日電話で言いましたよね? 相談事は、直接会って、目を見て話さなきゃって。目を見て話すことでわかることがたくさんある。直接会って、目を見て話すことが一番大事なんだって。だから私、こうして名古屋まで来たんですよ?」
「うっぐー」
マイナス10ポイント。
ちなみに、志村の現住所を、望月はもう調べてあった。このレストランから、タクシーで10分もかからない距離である。
15分後。
美桜と望月の二人は、とある住宅街にいた。美桜は、一人で行くつもりだったが、望月は「いざという時、弁護士が同行してる方が安全だから」と言い、そこはついに譲らなかった。
目的地に建っていたのは、白いモルタルの壁に青いトタン屋根の二階建て家屋だった。こんもりとした緑の植栽に囲まれている。建物の右手に鉄製の外付け階段がついていて、どうやら二階部分はアパートとして運用されているようだった。
「ここ、ですか? 引退してるとはいえ、あんまり、ヤクザの大親分って感じの家じゃないですね」
美桜が言う。薄汚れた外壁。痛みの酷い雨どい。階段脇の郵便ポストには茶色の錆が浮いている。そして、建物全体から、野焼のような、何かが燻されているような匂いがした。
「なんか、変な臭いがしませんか?」
そう美桜が言った直後だった。パンパンパンと連続で破裂音がした。それと同時に、二階の真ん中の玄関前から、ブワッと赤い炎が上がった。
「! 望月先生!」
「え? 火事?」
「先生! 消防車を呼んでください!」
美桜は、アパートに向かってダッシュした。望月は、急いで携帯を取り出し、消防に電話をかける。美桜は、一階の玄関ドアの呼び鈴を押す。が、一階の部屋にはどこにも灯がなく、呼び鈴の応答もない。建物脇の外階段を見る。煤けた色の煙が、二階から地上に向かって、ゆっくりと降りて来る。アパートの裏手へと美桜が走るのを追いかけて、望月も走る。二階の窓を見上げる。
「!」
一部屋だけ、灯りが点いている。
(誰かいる!!)
そう望月が慄然としたのと、部屋の中からつんざくような悲鳴が聞こえてきたのが、ほぼ同時だった。
美桜は、悲鳴を聞くと、おもむろに、近くに植えられていたケヤキの木に登り始めた。
「美桜ちゃん!?」
二階の高さまで一気に登る。その身のこなし、まるで『キャッツアイ』か『ルパン三世』の峰不二子だ。望月は思わず携帯の動画撮影ボタンをタップする。美桜は、太めの木の枝を選んでぶら下がり、前後に体を揺らした。そして、大きく反動をつけると、悲鳴の聞こえた部屋の窓に向かって、勢いよく飛んだ。