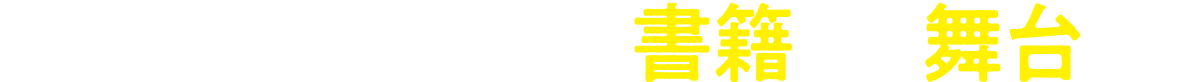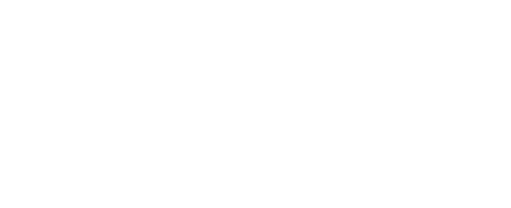書式設定
- 文字サイズ
-
- 小
- 中
- 大
- 特大
- 背景色
-
- 白
- 生成り
- フォント
-
- 明朝
- ゴシック
- 組み方向
-
- 横組み
- 縦組み
書式設定
「第10回」
7
十七時。
広中美桜と母の琴子は、平日はいつも、美桜の「グレイス」出勤の時間に合わせて世間より少し早めに夕食を摂る。本日のメニューは、朴葉寿司。朴の木の葉で酢飯を包み、中には鯖の酢漬け、きゃらぶきの煮物、錦糸卵が入っている。
同じく十七時。
広中大夏の毎日に、ルーティンはあまり無い。今は自室の万年床にうつ伏せになり、刺された尻の痛みと挫いた足の痛みに耐えている。金を節約したくて薬局に出向かなかったせいで、痛み止めは切れてしまっている。
十七時五分。
「美桜ちゃん。畦地さんが無理なら、ヤマモトさんはどう?」
琴子が唐突に言い出し、美桜は椅子から転げ落ちそうになった。ちなみに、畦地というのは、美桜の初恋相手の大学教授だが、この春、とある殺人事件に一緒に関わり、共に危険な体験をし、その過程で、彼には既に生涯を約束したパートナーがいることを知った。それも同性の……男性のパートナーだ。事件は無事に解決したが、恋は無惨に潰えた。その経緯のすべてを琴子は知っていて、
「だったら美桜ちゃん。早く二度目の恋を見つけないと」
と、余計なお世話な発言を繰り返していた。
が、それにしてもだ。いくらなんでも「ヤマモト」を勧めるのは有り得ないと美桜は思う。
「お母さん。あの男はね、名古屋で一番悪い人だからね」
「あら、美桜ちゃん。それは誤解よ。あの人、うちの『あんかけパスタ』を、ちゃんと『パスタ』って呼んでくれたのよ。『あんかけスパ』じゃなくて。絶対、良い人だわ」
美桜が反論すると、琴子もムキになる。
「お母さん。あの人、ヤクザだよ? 反社会的勢力の人間だよ?」
「あら、美桜ちゃん。それも誤解よ。あの人、帰りにお母さんに名刺くれたのよ。ほら」
琴子がその名刺を見せてくる。
「野球部『栄ガッツ』監督 ヤマモト」
「何、これ。ふざけてる」
美桜はその名刺をゴミ箱に捨てる。それを琴子はすぐに拾い上げる。
「美桜ちゃん。お母さんはこう思うの。短気ですぐにカッとなる美桜ちゃんには、ヤマモトさんみたいにクールで思慮深い人がお似合いなんじゃないかって」
そして急に、
「そういえば、この前、お父さんとね! 美桜ちゃんの未来の結婚相手についてお話ししたのよ?」
と、目を輝かせる。
「……この前っていつよ」
「この前はこの前よ。ええと、ええと……美桜ちゃんの入学式の日!」
琴子が言っている入学式というのは、なんと美桜の小学校の入学式だ。つまり、もう四半世紀以上前の話だ。
「その時、お父さん、何て言ったと思う?
美桜に苦労させないくらいの経済力があって、
美桜を守れるくらい強くて、
気難しい美桜を毎日笑わせるユーモアのセンスもあって、
顔はジャガイモみたいでも良いけれどきちんと清潔感はあって、
家事が出来て、
育児にも協力的で、
結婚しても美桜と一緒に頻繁に実家に遊びに来てくれる人……
って言ってた!」
琴子は、両手で指折り数えながら、熱弁する。
「お父さんがあんなに欲張りなこと言うの、お母さん、初めて聞いたわ」
「へえ、そう」
美桜はうんざりする。父の話なんか聞きたくない。が、琴子自身は、辛い記憶だけを上手に忘れ、今もまだ父と同居しているかのような話し方をする。仕方なく美桜はいつも、琴子の楽しい気持ちに水を差さないよう、自分の感情を顔には出さないようにする。
十七時十分。
大夏は、うつ伏せのまま、スマホをチェックする。メリッサたちから、
「美桜姉ノ動画、観たゾ。サスガダナ! オマエとは月とスッポン! どまつり万歳!」
というメッセージが来ている。携帯を投げ出し、深いため息をつく。
十七時十五分。
「ちなみに、お母さんはその時何て言ったかと言うとね……」
琴子はまだ、同じ話題を続けている。
「お父さんみたいな人、って言ったんでしょ?」
「そうなの! 美桜ちゃん、大正解!」
もう延べ二十回は聞いた話だ。
「そしたらお父さんね。『え? 僕みたいな人? そんな人で良いの?』とか言うのよ? 失礼しちゃうわ。だから私ね。きちんと説明してあげたの。『私は、お父さんみたいに、遠い人に優しく出来る人が好きなのよ』って」
これも、二十回以上は聞いた話だ。
美桜も、一度だけ、父から直接聞いたことがある。
「本当に優しい人は、遠い人に優しい人のことだ」
何を言っているのか、幼い美桜には理解出来なかった。なぜ、突然そんなことを言い出したのかももう覚えていない。でも、不思議とその言葉は耳の奥にずっと残っている。
それから急に、今日のヤマモトとの会話の最後の部分を思い出す。
「真犯人は、追い詰められましたね。こうなったら、次は本当に誰かを殺さないと、ここまで頑張って実行してきたことが全部無駄になってしまう」
「……どうして私にそんなことを話すんですか?」
「別に、深い意味はないですよ。私はどまつり関係者じゃないし、本番も見に行くつもりはない。誰が殺されたところで、私には遠い人です」
「本当に優しい人は、遠い人に優しい人のことだ」
どこかで父が美桜に言う。
「お父さん、美桜には優しい人になって欲しい。だから、覚えておいて欲しい」
その数年後に家族を捨てるくせに、父は美桜に言う。
「優しさは、遠い人に」
十七時三十分。
大夏は、尻と足が痛い。
十七時四十五分。
大夏は、尻と足が痛い。
十八時ちょうど。
大夏は、尻と足が痛い。
十八時十五分。
大夏は、もぞもぞと万年床から起き上がる。十九時には「タペンス」を開けなければならない。いつもなら十分かからない距離だが、今日はかなり時間に余裕を見る必要がある。洗面台まで這うように移動し、顔を洗い、歯を磨き、髪を整える。大夏にも、バーテンダーとしての最低限のプロ意識はあるのである。
十八時五十分。
大夏は「タペンス」の入っているペンシル・ビルの階段を、一段一段、注意深く登る。
三階まで来る。事件の記憶がフラッシュ・バックする。大夏を襲った暴漢は、あの夜、ここに潜んでいた。刃物。智秋の悲鳴。刺された瞬間の熱い痛み。転落。最悪の記憶だ。それを振り払うように通過し、四階へ。店内に入る。松葉杖は、冷蔵庫の横に立てかける。カウンター脇の棚から、一枚のレコードを取り出す。この店に就職した時にオーナーから出されたたった一つの条件。それが、
「十九時の開店と同時に、ジャクリーヌ・デュプレのチェロ協奏曲をかけること」
だった。
「それ以外は自由にして良い。客がいなければ早仕舞いしても構わない。ただ、十九時ちょうどには、必ずこのレコードをかけてもらいたい」
理由は今も不明だ。
レコードをターンテーブルに載せる。針を落とす。仄暗いクラリネットの音が店内に流れる。良い音だ、と大夏は思う。が、それ以上に、尻が痛い。足も痛い。
(今夜は、このレコードが終わったら閉店しちゃえ)
そんなことを考える。が、レコードをかけてからわずか三十秒ほどで、店のドアベルがカランカランと鳴った。振り向くと、半分開いたドアから、【一】《いち》【見】《げん》と思しき男が店内を見ている。
「やってます?」
(こんな早い時間に、男の一人客?)
不審に思いつつも、
「やってますよ。どうぞ」
と、大夏は男に頭を下げる。四十代後半くらいだろうか。ブランド物の白いシャツ。腕時計も高そうだ。男はカウンターに座ると、
「この店、音楽の趣味が良いね」
と、やや上からな雰囲気を漂わせながら言った。
「きちんと、アナログ・レコードを使用しているのが良いよ。人間の可聴域の音だけを取り出してデジタル処理をすると、深さとか音の温かさみたいなものまで削られてしまうからね。特に、ストリーミングのmp3とかは最悪だね。あんなものを聴きながら『音楽好きです』とか言ってる人たちは、耳が悪いとしか言いようが無いよね」
「音楽、お詳しいんですね」
大夏は無難な合いの手を入れる。
「それも、仕事の一部でね」
男は「やれやれ」という感じの仕草をしながら言う。「どういうお仕事なんですか?」と聞いて欲しかったのかもしれないが、大夏は鈍感な男だった。なので、水とメニューを出しながら、全然違う質問をした。
「お客さん、うち、初めてですよね? どうしてうちに?」
男は質問に答える前に、なぜか、店内をぐるりと見回した。まるで、防犯カメラや盗聴マイクを警戒しているかのような動きだった。それから、モゾモゾと体をカウンターに乗り出し、声を少し潜めて言った。
「この店に、水田智秋が飲みに来たんだって?」
「え? 何で知ってるんですか?」
「ふふ。彼女とは仕事仲間だからね」
「ええ? あなたも役者さんですか? げ、芸能人?」
「違うよ。でもまあ、僕も広い意味では同じ業界の人間というか……」
男の自慢げな説明を最後まで聞く前に、またしても店のドアベルが鳴った。こんな早い時間にまた客が? せっかく智秋についていろいろオフレコ話が聞けるかもと思ったのに! そんなことを思いながら大夏はドアの方を振り向き、入ってきた人物を見て驚愕した。
「ね、姉ちゃん!」
そこには、美桜が立っていた。
「え? え? なんで? なんで姉ちゃんがここに?」
が、美桜は大夏を見ていなかった。美桜は美桜で、驚愕の表情を浮かべてカウンターに座るブランド白シャツの男を見つめていた。そして、男の方もまた、顔面を蒼白にして美桜を見ていた。
やがて、美桜が先に口を開いた。
「あんた……『桜坂』にいたモラハラ夫?」
8
『桜坂』にいたモラハラ夫。本名を外東紘平という。四十七歳。名古屋大学を卒業して、東京の大手広告代理店に入社。現在の役職は、コンテンツ事業部の部付部長。ごくごく平均的な出世スピードである。
半年前に、名古屋を舞台にしたとあるダンス映画の仕事を上司から振られた。
・在名のテレビ局の周年記念映画である。
・どまつりとのタイアップが決定している。
・主演も水田智秋で決定している。
・君、名古屋出身だから、東海地区はいろいろ人脈あったよね?
・製作委員会に入り、出資や協賛の取りまとめや、告知PR関係を取り仕切って欲しい。大ヒットさせろとは言わないが、絶対に赤字は出さないように。
ざっくり、そういう内容の指示だった。既に大きな枠組みは出来上がっている仕事だし、難しい部分は無いと思った。それより、製作委員会の会議は常に名古屋で行われるので、今年は実家への帰省費用は会議の出張費で賄える。それが、外東には嬉しかった。
残念なことに、外東の事前の予想は当たらなかった。
まず、春。堀口芽衣という若い女性ADが、監督の「人間性」について、幹事会社のプロデューサーに「相談」をしてきた。
監督の名前は、元谷勝利。ちなみに彼をこの映画の監督に推薦したのは外東だった。理由は大きく三つ。
一つ。元谷勝利は売れっ子ではないのでギャラが安い。
二つ。元谷勝利は売れっ子ではないので、製作委員会や局のプロデューサーに対してわがままを言う心配が無い。
三つ。元谷勝利も名古屋出身なので、監督に抜擢する大義名分がある。
それともう一つ。これは、外東は誰にも言っていないが、実は外東と元谷はとある趣味の仲間でもあった。どうせ誰かに依頼するのであれば、なるべく自分の仲間で固めるのが賢い。外東は常々そう考えていた。その方がいざという時に何かと融通も利くし、恩を売っておけばいつかは利子を付けて返してもらえることもある。
堀口芽衣の「相談」への対応は、監督の推薦者である外東のところに回ってきた。彼は堀口芽衣を汐留にあるホテルのラウンジに呼び出した。そして、一杯千五百円もする珈琲を飲みながら、懇々と彼女を説得した。
「この映画に、何人の人間が関わっていると思う?」
「確かな証拠も無しに騒ぐのは、大人としてどうかな?」
「最悪、何億円という単位で赤字が出る可能性もあるんだよ? 君、その責任は取れないでしょう?」
「でも、あなたの責任感は素晴らしいと思う。この先、ぜひ別の映画やドラマでも、僕は君と仕事をしたいと思うな」
そんなようなことを話した。
理解をしてくれた、と思った。
が、その女性ADは、外東が思っていたよりも頭が悪かった。なんと、同じ「相談」を、この映画の主演に決定していた水田智秋にしたのである。二人は年齢が近く、別作品で意気投合した友人同士だったのだ。
「事実関係をきちんと調査してください。告発が事実なら、監督を降板させてください。それが無理だと言うなら、私がこの映画を降板します」
梅雨の真っ只中だった。水田智秋は製作委員会に突然の申し入れをした。人気の主演女優と、ギャラが安いだけの売れていない映画監督。製作委員会がどちらを優先するかは考えるべくもない。そもそも、ごく一部の例外を除いて、映画監督の名前など興行収入には何の影響も無いのだ。たった三十分の会議で、元谷監督には降板してもらうことになった。降板の説明係も、当然、外東だ。嫌な役目だったが、外東は大門にある高級焼肉屋の特上コースを元谷に奢ることで、平和に彼を納得させた。
(もう、これ以上のトラブルは無いだろう……)
そう安心したところで、次の事件が起きた。それも、これまでの二つとは桁違いの大事件だった。どまつりに対する脅迫。連続して起きた傷害事件。殺人の予告。愛知県警には捜査本部が作られ、どまつりの開催は風前の灯となった。どまつりが無くなれば、タイアップ映画のクランクインも無くなる。スタッフやキャストに対するキャンセル料だけが請求され、収入は一円も無い。
「大ヒットさせろとは言わないが、絶対に赤字は出さないように。一円でも赤字が出たら、君の次は無いよ」
そう言った上司の顔がありありと思い出される。
(なんてことだ……)
が、外東の立場で出来ることなど、現状、ほぼ無い。
公益財団法人にっぽんど真ん中祭り文化財団、名古屋市、愛知県警、そして、どまつり映画の製作委員会。四団体合同での会議が行われた。どまつりの開催を中止にした時の、経済的な損失はどのくらいか。どまつりの開催を強行して、本当に殺人事件が発生した場合はどういう事態になるのか。事件の情報を開示することで起きるであろう混乱。情報を開示せずに、今後、殺人事件が起きた場合の道義的責任の所在。財団の立場。財団を支援している行政の立場。警察の立場。在名のテレビ局の立場……細部までの意思統一は難しかったが、それでも、
「どまつりにダンサーとして参加予定の皆さんには、SNSなどへの書き込みは控えていただくという前提で情報を開示する」
ということだけは全員が合意した。
なるべく早く説明会の開催を、ということになり、外東は、映画のダンス・エキストラ・チームへの連絡担当となった。ちょうど、その日は、エキストラ全員がスタジオに集まっての練習と衣装チェックの予定だった。現場についているスタッフは、外東が大嫌いな女性AD・堀口芽衣だった。が、今はそんなことは言っていられない。外東は彼女に電話をかけた。
☆
「この衣装で問題無く踊れるかどうか、各自で確認してください。動きにくい箇所がありましたら、至急こちらで直しをしますので」
芽衣が大きな声で呼びかけると、ダンサーたちは、練習を中断して段ボールの周りに集まってきた。
「この衣装で問題無く踊れるかどうか、各自で確認してください。動きにくい箇所がありましたら、至急こちらで直しをしますので」
ダンサーたちが、自分の名前の付箋の付いたビニール袋を、段ボールから次々に取り出していく。すべてが取り出されて空になったタイミングで、松葉杖を両手使いしている男性が芽衣の前に立った。
「衣装、Lサイズで申請しました、広中大夏です」
「え?」
芽衣が驚くと、男性の方も、
「え?」
と驚きの声を上げた。この男性は、その怪我でどうやって参加するつもりなのか。ダンス・エキストラの役割を理解しているのだろうか。それをどう説明しようか。そんなことを考えていると、腰に提げていたADバッグの中で、芽衣の携帯が鳴った。
「ちょっとごめんなさい」
芽衣は男性に謝り、電話に出た。
「え……はい……そうですか……はい、わかりました」
短い電話だったが、内容は重たかった。芽衣は、自分の表情が曇っていくのを自覚した。携帯を切ると、芽衣はスタジオの中にいるダンサーたち全員に声をかけた。
「すみません。今、緊急の連絡が入りました。どまつりの実行委員会の方から、緊急で、皆様にご報告しなければいけないことが起きたそうです」
スタジオ内が少しざわついた。
「とはいえ、この人数全員は、どまつりさんの会議室には入りきれません。皆さん、元々五人ずつの組でオーディションを受けられていたと思います。なので、その五人からお一人ずつ、代表の方だけ、今からどまつり実行委員会さんのビルの大会議室までご移動をお願いします」
「チームの代表?」
「はい、どなたか一名」
芽衣に言われて、ダンス・エキストラの各チームはあちこちで小さな輪を作って代表者を決める話し合いをした。と、また芽衣の携帯が鳴った。相手は先ほどと同じ、外東だった。彼と話すのは好きではないが、無視するわけにもいかないので電話には出た。
「別件だけど、水田智秋さんが襲われたバー、どこか知ってる?」
「え?」
「堀口さん、彼女とは仲良しなんでしょう? 何も聞いてないの?」
なぜ、そんなことを質問するのだろう。芽衣は訝しく思った。が、立場的に、あれこれこちらから詮索をするのは躊躇われた。ちなみに、そのバーの名前を芽衣は知っていた。なぜなら、事件当日、その店に一緒に行こうと智秋から誘われていたからだ。が、クランクイン直前の時期、下っ端のスタッフには雑用が山のようにある。それで、残念ながら断ったのだった。
「女子大小路にある、タペンスっていうバーだと思います」
知っていることは正直に話すことにした。
「そか。ん」
外東は、礼も言わずに電話を切った。相変わらず、感じの悪い男だ。このことを智秋には言うべきだろうか。そういえば、あれから智秋は現場に一度も来ていない。ダンスの練習にも来ていないし、衣装合わせは延期になったと聞いている。智秋の方には怪我は無かったはずなのだが、大丈夫なのだろうか。やはり、襲われたショックは大きかったのだろうか。一度、事件について送ったお見舞いLINEは、既読にはなったが、返信は無い。だが、下っ端スタッフのひとりでしかない自分が、それ以上の何かをするのは少し躊躇われた。それに、予算削減を理由にフォースADがいない現場だったので、その分、サードとセカンドADの雑務は膨大だった。時間的な余裕がまったく無かった。
「残った皆さんは、衣装を着て踊ってみてくださいね! 当日に踊れないでは困りますからね!」
思考を切り替え、明るく大声で指示を出す。金色をアクセントにした煌びやかな衣装。オレンジ色の可愛らしい尻尾が付いている。
「スミマセン、シャチの尻尾、踊ッテルとチョット邪魔デス」
褐色の肌の外国人ダンサーが、芽衣に意見を言いに来る。
「シャチじゃなくてエビですねー」
一応は訂正をしつつ、芽衣はダンサーの背後に回ってその尻尾を彼女に当ててみる。
「もう少し尻尾は短い方が良さそうですね。衣装さんに、調整のリクエストをしておきます」
「アリガトウ」
「メリッサ」と名札を付けた女性が頭を下げる。他にも、法被の裾をもう少し短くして欲しい、ウエストのベルトがつるつるしていて解けやすい、踊ると肩がキツイ、などの意見をすべてメモしていく。人数が多いので、衣装チェック一つも大作業になる。その後、ダンサーたちを帰し、音響機器などを片付け、それから、回収した衣装を一つ一つ確認して段ボールに再梱包する。少し離れた場所で、別のスタッフたちが、
「軽く、飲みにでも行く?」
と話し始めたのが聞こえた。視線を向けると、荒井という同い年の男性スタッフと目が合った。彼はちょっと躊躇う仕草を見せた後で、
「堀口さんも来ます?」
と遠慮がちに訊いてきた。彼は、これまでの別現場ではずっと、芽衣のことを「芽衣ちゃん」と呼んでいた。が、あの一件から数日後、彼の呼び方が「堀口さん」に変わった。距離感も、変わった。その理由を彼に尋ねたことは無い。訊いても正直に答えてはくれないだろうと芽衣は思っている。
(あの時、私はどうするのが正解だったのだろう……)
今も、時々、考える。
深夜のスタッフルーム。衣装担当のスタッフから送られてきた膨大な数の候補画像をせっせと整理していた。監督はとっくに帰宅している。
「使えそうなところを厳選したら、共有フォルダにアップしておいてくれ。空き時間に見ておくから」
そう言われていた。指定の共有フォルダを開くと、中に大量の子フォルダがアップされていた。機械音痴の監督は、どうやら映画製作とは無関係の個人フォルダまで共有範囲に設定しているようだった。
(まいったな、もう)
そう内心でため息をつきながら、監督のプライベートのフォルダは開けてしまわないよう、慎重に目的のフォルダを探した。
「衣装合わせ・永久保存版」
そうネーミングされたフォルダを見つけた。「永久保存版」という単語に違和感を覚えたが、要はこれは「決定したもの」という意味だろうか。まだ候補段階の画像もここにアップして良いのだろうか。それともこのフォルダの中に、「候補」と「決定」といったような子フォルダが更に入っているのだろうか。
フォルダを開けてみた。
その瞬間、心臓が跳ね上がった。
小さな悲鳴も出た。
なんだ、これは。
なんなんだ、これは。
「堀口さんは、どうします?」
荒井がもう一回尋ねてきた。返事をする前に、携帯が鳴った。また、外東だろうか。(ごめんなさい)というジェスチャーを荒井にしてから、芽衣は携帯を見た。電話の相手は、外東ではなく、水田智秋のマネージャーからだった。
「堀口さん、すみません。一つ、頼まれていただきたいのですが」
久保田という年配のマネージャーが、いかにも申し訳なさそうな声で言う。
「はい。どんなことでしょう」
「オフレコでお願いしたいんですが、実は今、水田は名古屋で入院しておりまして」
「え?」
驚きのあまり、大きな声が出てしまった。それからすぐに「オフレコ」と念押しされたことを思い出し、周囲を見回しながら小声で尋ね直した。
「智秋さん、にゅ、入院してるんですか?」
「はい。事件に遭った翌日、警察で事情聴取がありましてね。それはまあ、あって当たり前のことなんですが、それ終わりで部屋を出て、警察署の階段を降りようとしたところで、いきなり嘔吐しまして」
「え……」
「そして、失神してしまいまして」
「ええ?」
「それで、緊急搬送されてまして、そのまま入院しました。精神的なストレスと、あとは過労もあるのではと」
そんな大事になっていたなんて、全然知らなかった。久保田は淡々と先を続ける。
「このことは、映画の製作委員会の上の方の方々しか知らないんですが、クランクインも迫ってきましたし、水田にはそれまでに元気になってもらわなければならないんです。でも自分は、別件の仕事で東京に戻らなくてはならなくて。それで、堀口さん。一度、水田の見舞いに行っていただけないですか? 今、名古屋にいる水田の友人って、堀口さんしかいないので」
☆
芽衣が、膨大な雑務の間を縫って智秋の見舞いに行けたのは、マネージャーから電話を貰った翌々日の夕刻だった。もっと早く駆けつけたかったのだけれど、智秋の入院見舞いだということを周囲に話せない以上、時間をこじ開けるのが本当に難しかったのだ。
鮮やかな夕焼けが、名古屋掖済会病院の壁面をほんのりと染めていた。外来受診の時間は既に終わっていて、エントランスすぐの吹き抜けロビーは閑散としている。面会の手続きをして、入院棟に。マネージャーから教えてもらった個室のドアをノックする。中から返事は無い。そっとノブを回すと鍵はかかっておらず、すんなりドアが開く。水田智秋はベッドではなく、窓際の椅子に座って外をぼんやりと見ていた。
「智秋さん。芽衣です」
声をかける。智秋は、ゆっくり振り向き、しかし何も言わず、やがてまたゆっくりと窓の外に視線を戻した。芽衣の知っているいつもの智秋とは別人のような雰囲気で、彼女は戸惑った。中に入り、ドアを閉め、ベッド脇にある丸椅子に腰を下ろす。
智秋はまだ外を見ている。
「お体の具合、どうですか?」
芽衣が尋ねる。
「身体は全然平気。そもそも私、殴られてもいないし刺されてもいないし」
「良かった」
「何が良かったの?」
「それはだって」
「また私だけ無事で、それの何が良かったのかな」
「え? また?」
芽衣は、智秋が何を言っているのか理解出来なかった。
「またって、どういうことですか?」
が、智秋はそれについては説明をしなかった。ただ少し、寂しげな微笑みを浮かべただけだった。
しばらく、互いに無言のまま、座っていた。何か話さなければ、と芽衣は思う。が、今、どういう話題が相応しいのか、それが芽衣にはわからなかった。迷った末、芽衣は大夏の話をすることにした。
「そういえば、タペンスの彼、ダンスの練習に復帰してましたよ」
努めて明るい声で話す。
「まだダンス自体は出来ないですけど、『本番までには振りを完璧に入れる』って言って、一生懸命動画で振りの撮影をしてました。『智秋さんの映画を、俺が傑作にするんだ!』って、大きな声で周りの人たちに言ってました。彼、ちょっと面白いですよね」
努めて楽しい雰囲気で話す。しばらく智秋はそれにも答えなかったが、やがて、
「私、見たんだ」
とポツリと言った。
「大夏くんがね、落ちていくところ。上から」
「はい……」
「怖いよね、落ちるって。私、また、あの音が聞こえるかと思った」
「あの音?」
「うん、あの音。ぐしゃり……って」
「?」
話の内容がわかるようでわからない。それを細かく質問して良いものか。質問して欲しいから智秋は言葉にしているのか。だが、芽衣がそれを尋ねるより前に、智秋が芽衣の方にくるりと向き直った。
「芽衣ちゃん、ごめんね。芽衣ちゃんが、私からすごく遠い人なら、私だって一生懸命気を遣って頑張ると思う。心も元気なフリをすると思う。でも私、芽衣ちゃんのことは近い人だと思ってるから。とっても近い友達だと思ってるから。だから、ごめん。今日は帰って。本当にごめん」
そう言って、智秋は芽衣に頭を下げた。
「……わかった。じゃ、私、帰るね」
そう言って、芽衣は立ち上がる。わざと、敬語はやめて。今までも、一緒にお酒を飲んだ時などは、最初が敬語で途中からそれをやめていた。智秋が有名人過ぎて、なかなか、最初から距離を詰めるのは難しかった。そのことを、何度も智秋にはからかわれていた。
「どうかお大事に」
「ありがとう。明日には退院するつもり」
そう言って智秋が微笑む。
「うん。でも、無理はしないで」
芽衣は小さく手を振り、部屋から出る。
(何があったんだろう)
わからない。
(またって、何が、また、なんだろう。音って、何の音なんだろう)
わからない。
(そういえば、放火事件の話、しなかった……)
夕べ、栄で放火事件があったこと。狙われたのが、どまつりの学生委員長だったこと。犯人がその場で逮捕されたこと。なので、どまつりは無事開催されることになり、それはイコール、智秋も安全になったのだということ。そんな「良いニュース」を伝えて彼女を元気付けたいと思っていたが、出来なかった。
(私、何の役にも立っていない)
力なく俯いて、芽衣は廊下を歩く。俯いていたせいで、とある男と至近距離ですれ違ったことに芽衣は気づけなかった。黒いキャップを被り、マスクをし、顔をなるべく見られないようにしていたが、普段の芽衣ならその男には気づいただろう。
男は、今、芽衣が来た方角に歩いていく。
水田智秋の病室のある方向に。
9
白いリノリウムの廊下を歩く。なるべく自然な速さで。足音が響かないよう、靴底を少し意識して。
目指す病室の手前で、一度、立ち止まる。スマホを取り出し、メール画面を確認する。
『南棟2階の215号室』
それから鞄を開け、中身を確認する。両刃で殺傷力が高いダガーナイフ。硫酸の入った小瓶。どちらを使うか、まだ決めかねていた。
殺すか。
顔に硫酸だけで十分か。
腕時計を見る。面会時間の終了まで、あと十分。老夫婦とその息子らしき三人組が通過する。配膳車が通過する。聴診器を首から下げた看護師が通過する。そこで、人通りが途絶えた。
(今だ!)
ドアに手をかける。そのまま、自分の家族の病室かのように堂々と中に入る。こそこそする方が逆に目立つ。
部屋の中は暗かった。灯りが一つも点いていない。
こんな時間からもう寝ているのか? それとも、トイレにでも行っているのか? いずれにせよ、これからやることにたいした変わりは無い。部屋にいないのなら、待ち伏せをするだけのことだ。鞄の中に手を入れる。ダガーナイフの柄が先に手に触れた。
(なるほど。やる以上はとことんやれ、ということか……)
男は覚悟を決めた。ほの暗い室内に向かって目を凝らす。奥のベッド。布団が、人の形に盛り上がっている。
(躊躇うな! 一気にやれ!)
そう自分を𠮟咤する。
ダガーナイフを取り出すと、ベッド脇まで一気に走った。利き手である右手を振り上げ、左手で掛け布団を一気に引き剝がす。そして次の瞬間、渾身の力でナイフを真下の人間に向かって突き刺した。
ザクリ。
明確な手応え。だが、予想していたのとは違う手応え。
そして悲鳴。
つんざくような。だが、予期していたのとは異なる悲鳴。それは、水田智秋のそれではなく、男の悲鳴だった。
ベッドで寝ていたのは男性だった。尻と足にはギプス。胸と腹の部分には分厚い漫画雑誌を巻き付けている。ダガーナイフは、男の尻のギプスに突き刺さっている。刃のギザギザとした部分が引っかかり、抜こうとしても抜けない。
と、パチリと病室の灯りが点いた。誰が点けたのか? が、それを確認する前に、目の前の刺した相手と目が合った。知っている男だった。
「いれえ! いれえよ、姉ちゃん!」
男が泣き叫ぶ。ダガーナイフの先端が尻に刺さったのだろう。前は普通の包丁。それも、やや小ぶりなタイプだった。
「おまえ、あの時のタペンスの……」
呆然とした口調で彼は言う。激しく混乱する。なぜ、この男がここにいるのか。なぜ、この男が、水田智秋の病室のベッドに寝ているのか。
「なぜ……」
あれは、ほんの数日前のことだ。女子大小路にあるペンシル・ビルの階段で、彼はその男を刺した。刺して、階段から突き落としたのだ。
今、彼が刺した相手。それは、広中大夏だった。
*******************
…大夏を刺したのは誰?そして事件の真相は…
気になる結末は書籍でお楽しみください!
~女子大小路の名探偵 新章~
死は、ど真ん中に転げ落ちて
2025年2月下旬、河出書房新社より刊行決定!書籍情報はこちら