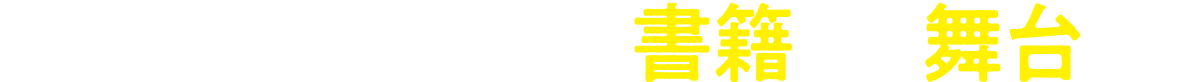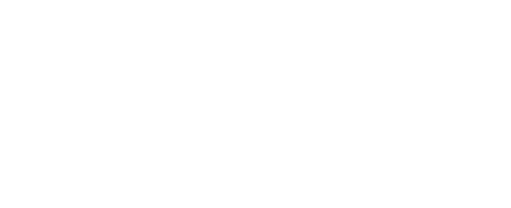書式設定
- 文字サイズ
-
- 小
- 中
- 大
- 特大
- 背景色
-
- 白
- 生成り
- フォント
-
- 明朝
- ゴシック
- 組み方向
-
- 横組み
- 縦組み
書式設定
「第5回」
3
「昨日の話ですけど。あれはもう、無視してもいいんじゃないですか?」
運転席の社員が、唐突に話しかけてきた。
「約束したと言われても、あの時とは事情が違うわけですし」
黒のワゴンは、桜通りから日銀前の交差点を右折し伏見通りに入っていた。十車線もある広い道の真ん中には、青々と緑の葉を茂らせた街路樹が並び、通りの両側には、窓に陽射しを白く反射するオフィスビルが林立していた。
「なるほど。おまえが俺なら、そうするわけだな?」
ヤマモトは静かな声で答えた。
「そして、俺はおまえのことをこう思うようになる。田辺明という男は、状況が変われば、一度交わした約束を簡単に反故にする男だ、と」
「!」
社員の背中に緊張で力が入るのがわかった。ヤマモトはそれ以上、言葉を足さなかった。
☆
錦の繁華街から、少しだけ桜通り方面に外れた七間町通りに、その建物はあった。コンクリート打ちっぱなしの外壁。四角く武骨な二階建て。天然石を高く積んだ外塀と、電動開閉式のガレージ。そして「中京興業」という看板。鉄製の堅牢なドア横にあるインターホンを鳴らすと、右上にある防犯カメラの下に、赤い点が数秒灯る。そして、ガチャンという鈍い音と共に扉のロックが解除される。
志村椎坐は、最奥にある個室にいた。
ちなみに「椎坐」と言う名前は「しいざ」と読み、本名だそうだ。彼の親が、皇帝ジュリアス・シーザーを意識して名付けたらしい。暗殺された男の名前を付けるなんて親の教養が疑われるな……と明は思っていたが、もちろん口に出したことはない。志村自身は、椎坐という名前を随分と気に入っているらしかった。
明は、黒のアタッシュ・ケースを抱えるように持ち、ヤマモトのすぐ後ろに付いて、一緒に志村の部屋に入った。志村は、大きく突き出た腹の前で、一本六万円するというチタン削り出しのパターを構えていた。明がアタッシュ・ケースを開くとヤマモトは中から分厚い白の封筒を手に取り、志村に差し出した。志村はパターを自分の腹に立てかけ、封筒の中を覗く。そこには、帯封付きのままふたつ……二百万円が入っていることを明は知っていた。志村は「ふん」と鼻を鳴らすと、それを無造作に自分のデスクの上に放った。
「相変わらず、おまえのところは景気が良いようだな」
陰気な声で志村は言う。
「オヤジの後押しのおかげです」
そう言ってヤマモトは頭を下げる。
「つまらん世辞を言うな。俺ではなく、浮田先生んところの三代目の後押しのおかげだろ」
不愉快そうに言うと、志村はまたパターを手に取り、コツンとボールを打った。ボールは、カップの直前で右にスライスし、外れた。
浮田先生んところの三代目とは、七年前に県議選に立候補してトップ当選した浮田一臣のことである。一臣は、三代続く政治一家の長男だった。ヤマモトは、大学を卒業したがあえて就職はせず、しばらく栄のバーでアルバイトをしていた。そして、浮田一臣の初選挙の時、ボランティアとして使って欲しいと彼の選挙事務所を訪ねた。精力的にビラを配り、選挙カーを運転し、街頭演説の聴衆が足りなそうな時はサクラを集め、一臣の演説動画を上手に撮影し、編集し、宣伝に活用した。すぐに一臣の信頼を得て、金銭の管理もある程度は任されるようになった。当選後、ヤマモトは浮田一臣の公設秘書になるだろう。周囲は皆、そう思っていた。が、ヤマモトはその選択をしなかった。ヤマモトは、浮田家に書いてもらった紹介状を手に、当時、「錦のシーザー(皇帝)」を名乗っていた志村の元を訪れた。以来、彼は外向きには、志村の舎弟ということになっている。
別のボールをセットする。パターで打つ。先ほどと同じように、ボールは、カップの直前で右にスライスして外れる。志村はパターを床に投げ捨てた。
「正直なところ、俺は、おまえのようなコアタマの良い金儲けタイプは好きじゃない。俺は、ゲンコツ一つでのし上がってきた男だからな」
ヤマモトは何も表情を変えない。
「おまえ、喧嘩は強くないんだろ? なら、なんでそのまま、政治の世界に行かなかったんだ?」
「自分にも夢がありまして」
「どんな夢だ?」
「日本を、元気にしたいと思いまして」
「ああん?」
志村が軽く凄んでみせる。だが、ヤマモトはそれ以上、夢についての説明をしようとはしなかった。そもそも「日本を元気にしたい」という大言が本気かどうか、明にはわからなかった。志村も同じだろう。やがて志村は肩をすくめると、
「ま、俺は、おまえが毎月こうやって金を稼いでくるなら、それで良い。おまえの夢にまで文句は言わんよ」
と言った。ヤマモトが小さく頭を下げる。志村は先ほどの封筒を持ち上げ、デスクの引き出しの中に入れた。それから急に、意地悪なイタズラを思いついた小学生のように、性格の悪そうな笑みを浮かべた。
「ただな、ヤマモト。この世界、金儲けだけじゃダメだぞ。いざという時には『殺し』くらいやれんと、この世界では相手にされない。わかるか?」
「……」
「ヤマモト。ちゃんとわかっているのか?」
「はい」
「『はい』と言ったな? この俺に、『はい』と」
「はい」
ヤマモトは、相変わらず、感情の変化を見せなかった。静かな声のまま、彼は答えた。
「いざという時には、『殺し』も頑張らせていただきます」
「ふは」
志村は軽く笑った。
「ちなみに、おまえの言う『いざという時』とは、どんな時だ?」
「オヤジのために、必要になった時です」
「なるほど。じゃあ、俺が命じた時は、おまえは『殺し』もやるんだな? 金儲けだけでなく」
「はい」
ヤマモトは、躊躇いもなく答える。
「ふは」
志村はまた、軽く笑った。色の悪い舌で自分の上唇を舐め、それから、ヤマモトの肩をポンと叩いた
「これから、女の家に行く。ヤマモト、俺の運転手をやってくれや」
「あの、運転なら自分が」
明が、思わず言う。
「俺はヤマモトに言ってんだ」
志村はヤマモトを笑顔で見たまま言う。
「かしこまりました。すぐに車を回してきます」
ヤマモトは返事をすると、すぐに志村の部屋から出ていった。
☆
運転席で、ヤマモトは終始無言だった。志村は、ヤマモトの後頭部を後部座席から眺めながら、ずっと同じことを考えていた。
(なぜ、俺はこいつが嫌いなんだろう)
頭は良い。
度胸も良い。
ヤクザの世界に入るのに、先に、政治家から推薦状をもらってくるなんて、普通の発想ではない。
口も固い。
いつもポーカーフェイスなのも良い。
そして、金儲けが上手い。まだ若いのに、今や幹部たちより多くの上納金を志村に差し出してくる。
ずっと、有能な部下が欲しいと思っていた。シマを維持し、拡大していくのに、有能な部下は不可欠だ。最近では、知多半島の西岸を根城にした連中が、じわじわと名古屋に勢力を拡大してきている。シノギのメインは、海岸線に近いという地の利を生かした密輸だろうか。噂ばかりで確かな情報が手に入らない。暴力だけでなんとかなる時代はとっくに終わった。これからは、きちんとビジネスの出来る人間こそが必要だ。そんな時、ヤマモトが現れた。有能かつ、地元の有力な政治家ともパイプのある男だ。小躍りしたくなるような幸運のはずだった。しかし、ヤマモトが有能であればあるほど、志村の心は陰鬱になっていく。
(こいつをこの拳で殴り殺せたら、さぞかしスッキリするだろうな……)
そんな物騒なことを考える。もちろん、しない。自分は皇帝だ。名古屋随一の繁華街である錦の皇帝。ならば自分は、ヤマモトのような若者こそ上手に使いこなす男でなければならない。
必要なのは、もっと大きなアメだろうか?
それとも、恐怖という名のムチだろうか?
志村の愛人は、栄の社会教育館の近くに住んでいる。一方通行の多いこの街では徒歩で移動した方が早いくらいだが、志村は運転手付きの車で行くのをいつも好んだ。開発の進む周囲から少しだけ取り残されたような、燻んだ雰囲気の中古のビル。一階は居酒屋。二階と三階は漫画喫茶。どちらも、年内に退去することで話は付いている。四階は空き店舗。そして、最上階の五階に、志村は自分の愛人を住まわせた。名前を、間宮沙知絵という。もともと彼女は岐阜に住んでいたのだが、志村の不動産ビジネスにおける「占有要員」を兼ねて、半年前にこのビルに引っ越しをさせられたのだ。
「オヤジ、着きました」
準備中の札が下がった居酒屋の前で車を止め、ヤマモトは後部座席のドアを開ける。
「おう」
「お迎えは、何時ごろにいたしましょう?」
「さあ、どうだろうな」
言いながら、車から降りる。このままずっと下で待っていろ、と命じてみようか。ただの嫌がらせだ。が、この男は顔色ひとつ変えないだろう。わかりましたと頭を下げ、その後、車の中であれこれと器用に仕事をするだろう。何も面白くない。俺が、自分の器の小ささに、少し自己嫌悪になるだけだ。バカバカしい。俺は、皇帝だ。大きな男でなければならない。
「ヤマモト。おまえも一緒に上に来い」
上着の襟を直しながら、そう命じる。
「たまには、茶の一杯くらい、飲んでいけ。大丈夫だ。俺の車に駐禁を切る警官はいない」
「わかりました」
ヤマモトは、無表情のまま頭を下げた。
このビルには、エレベーターが無い。沙知絵の部屋は、せめて四階にすべきだったかと思いつつ、志村は階段をゆっくり上がる。早く上がれば息が切れる。志村は、そういう姿を女に見せるのが嫌いだった。なので、ゆっくり上がる。ヤマモトは無言でついてくる。やがて、五階。玄関前に、簡素な表札が出ている。
「間宮沙知絵 美月」
窓から志村の車が見えていたのだろう。ドアベルを鳴らす前に、沙知絵が玄関のドアを中から開けた。
「お帰りなさい、あなた」
☆
間宮美月は、帰り支度をして、中学の教室を出るところだった。
「やっと終わった!」
「補習、だる~」
「スガキヤ寄ろうぜ」
同級生たちはそんなことを言い合いながら、固まって帰宅していく。美月は誰とも会話をせず、ひとり、教室を出た。友達はいないし、作るつもりもない。階段を下り、昇降口から外に出る。黒髪とセーラー服の紺色の襟を、太陽がじりじりと焼き始める。校庭ではサッカー部が、直射日光の中でボールを追いかけている。体育館からは、音楽や床を鳴らす足音と一緒に、笑い声や掛け声も聞えてくる。暑さのせいで、みんな頭がおかしくなっているのだろう。美月は足早に校庭を横切る。と、校門まであと少しというところで、後ろから自分の名前を呼ぶ声がした。
「間宮! おーい、間宮!」
振り向くと、担任の教師が、顔を真っ赤にしながら駆けて来た。痩せていて、ひょろりと背が高い。腕も足も長い。小さい顔に、黒縁の四角いメガネをかけているが、よく左右どちらかに曲がっている。汗っかきで、年中、額に汗を光らせている。この春に転任してきたばかりで、担当教科は体育。学生時代は器械体操でインターハイに出場したことがあるという噂だが、美月は興味は無かった。美月に追いつくと、担任の教師は肩で大きく息をしながら、
「間宮、今、帰りか?」
と、当たり前のことを訊いてきた。いちいち答えるのも面倒で、ただじっと彼の顔を見つめていたら、相手は何を勘違いしたのか、
「あ。先生の名前は、心太だ。心太先生って呼んでくれ。名前をまだ覚えてなかったことは気にしなくて良いぞ」
と言って、顔をくしゃくしゃにして笑った。心太というのは下の名前ではないか。なぜ、生徒に自分を下の名前で呼ばせたいのか。気持ち悪い男だなと美月は思った。
「ところで先生な。間宮に少し話があるんだ。今、ちょっとだけ時間良いか?」
心太は、美月を強引に連れ戻す。昇降口から中に戻り、進路相談室に。そして、部屋に入るとすぐ、窓を大きく開けた。が、その日は無風で、窓を開けただけでは部屋は暑いままだった。いつになったら、学校にもクーラーは付くのだろう。担任の教師は、椅子を引いて美月を座らせ、机を挟んで向かい側に自分も座った。
「ところで、間宮。志望校は決まったか?」
美月の予想通りの質問を、彼はしてきた。
「高校には行きません」
仕方なく、美月は答える。すると、男はまた、顔をくしゃくしゃにして笑った。
「そうか。なるほど。つまり、間宮には夢があるんだな。その夢に向かって一刻も早くチャレンジをしたいから、高校に行っている時間が勿体無いっていう、そういう前向きでポジティブな気持ちなんだな。先生、そういうのははっきり言って大好きだ。で、どんな夢なんだ? 間宮の夢、先生にも教えてくれないかな」
的外れにも程がある。美月はため息をつく。
「夢とか、何にもありません」
「そうか。そうなのか。まあ、夢っていうのは無理やり作るものじゃないからな。先生、そういう間宮の正直なところ、とっても良いと思ってるぞ」
なんなのだ、この男は。
私は、先生のこと、暑苦しいし気持ち悪いと思ってます。そう正直に言ってみようかと思った。が、おそらくそれを言っても、
「正直だな、間宮。先生、そういう間宮の正直なところ、とっても良いと思ってるぞ」
と言って、この男はまた、顔をくしゃくしゃにして笑うだろう。なので言わなかった。代わりに、
「じゃ、もう帰って良いですか?」
と言って、美月は立ち上がった。
「なら、帰る前に、一回だけダンスはどうだ?」
そう言って、彼は身を乗り出してきた。
「は?」
「心と体は連動しているからね。無心でダンスを踊ることで、見つかる何かもあると思うんだ」
「興味ありません。もう帰っていいですよね?」
くるりと背を向けて出口に向かう。その美月の左腕を、担任の教師はパシッと掴んだ。
「俺は、生徒みんなの『笑顔カウント』を記録してる」
「……は?」
何を言われているのかわからない。
「間宮。君はこの一か月、一度も笑っていない。だから、先生は、君のことが心配でたまらないんだ。先生は、とにかく、間宮には笑って欲しいんだ」
何を言われているのかわからない。男の腕を振り払う。
「いや、俺もね、生徒たちから『笑顔体操バカ教師』って呼ばれてることは知ってるよ? 最近はそれが、『笑顔ダンスバカ教師』になったことも、『笑顔どまつりバカ教師』になったことも知ってるよ? 確かに、先生も『どまつり』は初体験だ。どのくらい楽しいお祭りになるか、正直、先生にもわからない。でもな、間宮。それでもな、間宮。体験してみないとわからないことって、人生にはたくさんあると思うんだ」
本当に、何を言われているのかわからなかった。
体験してみないとわからないこと。
いくつかの映像が、美月の脳裏でフラッシュ・バックした。
たとえば、「お父さんはどこ?」と尋ねただけで、投げつけられた包丁。
たとえば、「あんただって、稼ごうと思えばお金を稼げるんだよ? もう12歳なんだから」と母から言われた日の不味そうな朝食。
たとえば、時々、家に来る偉そうな男が身体に付けている香水の臭い。その男が、いきなり美月の手に握らせてきた金。
「これで、2時間ほど遊んできな」
と言われた。黙っていたら、
「ありがとうございますって言いなさい!」
と、母からヒステリックに頭をこづかれた。あの時の惨めな痛み。
「先生。私、夢、ありました」
美月は、きちんと担任教師の方に向き直り、言った。
「母を殺して、母の愛人もついでに殺したいです」
「え……」
彼は絶句する。その表情を見ながら、美月は言葉を続ける。
「母から自由になったら、私、きっと笑えると思うんです。でもまだ私、中学生じゃないですか。普通にアルバイトもさせてもらえない年齢じゃないですか。だから、笑えないんです。笑いたくても笑えないんです。それともあれですか? 先生は、笑顔になるためなら、母を殺しても良いって言ってくれますか? くれないですよね? なら、笑顔カウントとか気持ち悪いことは言わないでください。そして、私のことは放っておいてください。じゃ、失礼します」
一回、嫌味のように深々と頭を下げ、そして美月は部屋を出た。担任の教師は、美月を追いかけては来なかった。校門を出て大通りを渡り、住宅街を歩く。いつもより徹底して日陰を歩く。日の光になんか、絶対に当たるものかと思う。太陽なんか嫌いだ。「心に、太陽を持て」みたいなことを言う人間も嫌いだ。あの担任は、いつか、そういう言葉を口にするだろう。想像するだけで、少し吐き気がした。岐阜駅からJRに乗って名古屋駅へ。夏休みのせいか、中央コンコースには家族連れの姿が多くあった。美月の足に、紺地に赤い金魚模様の浴衣を着た女の子がぶつかる。すぐに母親らしき若い女性が「ごめんなさい!」と頭を下げる。
「いえいえ。お裾分け、ありがとうございます」
そう言って、美月も頭を下げる。母親も女の子もキョトンとした顔になる。わからないよね? 心の中で思う。あなたたちにはずっとわからない。エスカレーターを降りて、地下鉄東山線に。駅二つで栄駅。この春から、母親の都合で、ずっとここから岐阜まで通学している。クラスメイトも担任も知らないけれど。
「ヤマモト。こいつが噂の美月だ」
家に入ると、母の愛人が来ていた。志村という、ヤクザ自慢の中年男が、美月の姿を見るなり、そう楽しそうに言った。そして、美月の目を覗き込むようにして、
「ちょうど今、おまえの話をしていたところだったんだよ」
と言い、すぐにまた、傍らの若い男を見て、
「なあ、ヤマモト?」
と妖しく目を光らせる。
(面倒くさいタイミングで帰ってきてしまったな……)
美月は心の中でため息をついた。志村がいるのはよくあることだが、若い男は初めて見る顔だった。志村が、その若い男をやたらと意識しているのが、中学生の美月にもすぐにわかった。母の沙知絵がずっと表情を固くしている。自分が帰ってくる前から、さぞかし嫌な雰囲気だったのだろう。志村がまた美月の方を振り返る。
「美月。こいつはヤマモトっていって、俺の部下の中では新顔なんだが、なかなか見どころのあるやつなんだ。どうだ。良い男だろう? や、でも、美月からしたら、ヤマモトくらい若くてもおじさんかな?」
こういう時、何と答えるのが正解か、美月は知っている。
「そうですね。おじさんですね」
努めて素っ気なく答える。予想通り、志村は嬉しそうに笑った。
「そうだよな。美月はまだ15だものな。俺もヤマモトも同じような『おじさん』だよな。だが、ヤマモトの方はどうかな。ついさっき、ヤマモトは俺に言ったんだよ。俺が命令するなら、自分は中学生とでもヤれるって」
「は?」
思わず、声が尖ってしまった。
「あなた!」
沙知絵が声を上げる。
「おまえは黙ってろ」
志村はいつも沙知絵には高圧的だ。
「なあ、ヤマモト。言ったよな?」
志村は、からかうような、それでいて敵意のこもったような目でヤマモトを見る。が、ヤマモトという男は、その敵意にあえて鈍感に振る舞うと決めているようだった。
「はい。子にとって、親の命令は絶対ですから」
彼は静かに答えた。美月は、少しだけ「意地悪」な振る舞いをしたくなった。
「子にとって、親の命令は絶対?」
わざと、同じ言葉を声に出して繰り返してみた。
「なるほど。その代わり、親は子に何かしてくれるんですか?」
母親がスッと目を逸らすのが見えた。
「ああ、すみません。つまらない質問でした。親がいないと子供は生まれてこないんだから、何もしてあげなくても親は親ですよね」
わざと、明るい微笑みを浮かべてみる。あまり挑発すると、志村という男は、横の若い男に「私とヤれ」と言い出すかもしれない。彼は、自分で自分の言葉にエキサイトしていく面倒なタイプだ。その前に、そろそろ退散しよう。
「私、これからまたすぐに出かけなければいけないんで、志村のおじさん、どうかゆっくりしていってください。何時までは帰ってくるなとかあるなら、それも教えてください。その時間までは絶対に帰ってこないんで」
そう言い終えて、さっと立ち上がる。すると、意外なことに、ヤマモトという若い男が質問をしてきた。
「美月さんは、部活とか、されてるんですか?」
「え?」
なぜそんなことを訊くのか。美月は振り向いてヤマモトを見た。ヤマモトは無表情で、彼の質問の意図が美月にはわからなかった。
「部活とは違うけど、ダンス、やろうかなと思って」
美月は答えた。
「ダンス? 美月が?」
母親が、驚いたように言う。
「担任の先生が、どまつり?とかいうお祭りに、チームを作って出るぞって。だから、私も練習して、それに出なきゃいけないんです。じゃ、行ってきます」
美月はそのまま外に出て、今来たばかりの道を、再び歩き始めた。
さて。
どこに行くべきか。