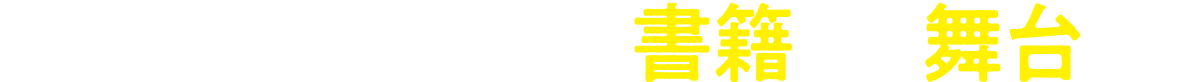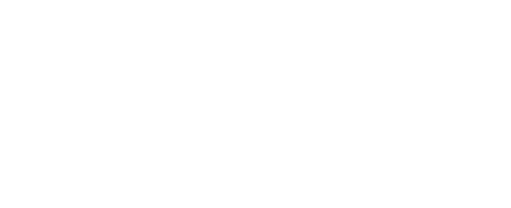書式設定
- 文字サイズ
-
- 小
- 中
- 大
- 特大
- 背景色
-
- 白
- 生成り
- フォント
-
- 明朝
- ゴシック
- 組み方向
-
- 横組み
- 縦組み
書式設定
「第4回」
9
第一回の合同捜査会議が終わって5分後。カタカナで「ヤマモト」としか名乗らない男は、運転手と二人、新栄三丁目にある自分の事務所に向かって車で移動をしていた。特徴らしい特徴のまるで無い黒のワゴン。法定速度プラス時速10km以内を頑なに守る安全運転で。
と、ヤマモトの携帯が鳴った。画面には「落語家」とだけ表示されている。
(ほー)
そう小さく呟いてから、ヤマモトは電話に出た。
「もしもし」
電話の相手は、挨拶的なことはすべて省いて、いきなり本題に入った。
「突然だが、どまつりの実行委員会相手に、何か仕掛けているのか?」
「は? 全然、話が見えませんが」
「私だって驚いたさ。でも、どまつり絡みで連続傷害事件の被害者が5人いて、そのうちの3人は、あんたと繋がりがあるって、所轄の刑事が発言をしてね」
「ほー」
「否定はしないのか?」
「や、否定はしますよ。どまつりと私の仕事は何の関係もありませんし、今後も関係する予定もありません。名古屋を愛する市民のひとりとして、どまつりの開催は毎年楽しみにしていますが、それだけです」
「ほー」
今度は、電話の相手が、ヤマモトと同じ相槌を使った。
「ちなみに、私と繋がりがあるとされた被害者は、どんな方なんでしょうか?」
ヤマモトが、丁寧な口調で尋ねる。
「うん。一人目は、17歳の女の子だ。名前は、平井野々花さん」
「全く存じ上げませんが」
「あんたがよく行くカフェのバイトらしいよ。あんた、彼女の店で、スタンプカードを作っただろう」
「スタンプカード?」
「一生懸命お願いしたら作ってくれたって。『とっても良い人でした』って」
「勘弁してくださいよ。そういうのは『繋がり』とは言わないでしょう」
「次が、大学三年生の女の子だ。名前は、荒瀬加奈さん」
「その子も、全く存じ上げませんが」
「この子は、錦のガールズBARで働いていて、ついこの前、コワモテの客に絡まれて怖い思いをしたらしい」
「あー」
「おっと。思い出したようだな。店では、新木カナって名前らしいぞ。あんた、オーナーとして、だいぶスマートな感じに彼女を助けたらしいじゃないか」
「従業員を守るのは経営者として普通でしょう? その私が、今度は彼女を襲う側に回る? 有り得ませんよ」
電話の向こうで、男が少し笑った。そして本題に入った。
「最後のひとりが、広中大夏くん」
「広中大夏?」
「そうだよ。今年の春に、あんたが一肌脱いでやった、あの広中大夏くんだ」
「……彼も、今年のどまつりに?」
電話の相手の男は、その質問には返事をせず、代わりにこんなことを言った。
「うちの刑事たちは、広中大夏とカタカナのヤマモトの組み合わせには、ちょっと神経過敏になっている。この間の事件から、まだあまり時間も経っていないというのに、また同じ組み合わせな訳だからね」
「私は何の関係もありませんよ?」
「そうだろうとも。私もそう思っている。だが、現場の刑事たちは疑うことが仕事だからね。彼らがいろいろと嗅ぎ回ると、全然違うことを見つける可能性もある。それで、老婆心ながら、私はこうやって電話をかけているんだよ」
「……ご心配、ありがとうございます、本部長」
「礼には及ばんよ。それより知事選挙、期待してるぞ。変なことで躓かないようにな」
それだけ言うと、電話は一方的に切れた。視線を上げると、運転を任せている社員と目が合った。
「ちゃんと、前を見て運転しろ。アキラ」
ヤマモトは静かな声で言った。
「はい、すみません」
アキラと呼ばれた社員が慌てて視線を前に戻す。ヤマモトは手でくるくると携帯を弄びつつ、今の短い通話について考えた。
(変なことで、躓かないようにな……か)
それは、確かに、そうだ。
そして、わずか一日前に事務所に来た、困った客について思いを巡らせた。
その客は、痩せこけた老人だった。
車椅子に乗っていた。
「しばらく、社長室に籠る。客も電話も取り次ぐな」
そう秘書たちに告げていたにもかかわらず、古株の社員が、わざわざヤマモトを呼びに来たのだった。その社員は、老人が何者か知っていた。正しい判断だった。
「お待たせして申し訳ありませんでした。大変お久しぶりでございます」
そう言ってヤマモトは深く頭を下げ、そして、人払いをした。二人きりになると、老人は不機嫌そうにヤマモトを睨み、それから、
「アイツが、帰って来たよ」
と、掠れた声で言った。ヤマモトは、彼の黄ばんだ前歯を見ていた。
「確かですか? あれからだいぶ時間も経ちましたし、見間違いという可能性も……」
「それは無い。俺は、この目で見たんだ」
そう言って、老人は煙草を取り出した。
「アイツの顔を、俺が間違えるわけがない」
「……」
ヤマモトのオフィスは全面禁煙だが、あえてそれは指摘しなかった。
「あの約束、まさか忘れたとは言わないよな?」
「もちろんです。自分は、受けた御恩は必ずお返しします」
「うん。おまえはそういう男だ」
老人は、煙草に火を付けると、肺胞の奥深くまで吸い、そして、ゆっくりと吐いた。
「一番、惨たらしい方法で殺せ」
「え……」
「指を切り、腕を切り、足を切り、両目を潰してから殺せ」
ヤマモトは小さく鼻を鳴らした。そして、今度は、声に出した。
「変なことで、躓かないようにな……か」
言ってから、ヤマモトはクツクツと小さく笑った。「殺しの依頼」を「変なこと」扱いするのは、さすがに「殺し」に対して失礼だと思ったからだ。
(しかし、俺は断れない……)
ヤマモトは、決断をした。
(殺すしか、ない……)
第二章
1
男が見つけたのは「袋」だった。
女が見つけたのは「フォルダ」だった。
中を開けると、彼の探し物とは、違うものが入っていた。
中を開けると、彼女の探し物とは、違うデータが入っていた。
男は、それを奪った。
女は、それをコピーした。
ふたりとも、その後どうするか、きちんと決めていたわけではない。咄嗟の行動だった。ただ、そうしなければいけないという確信があった。たとえ、それが、自らの不幸の引き金であったとしても。
人として。
2
名古屋駅から各駅停車で28分、快速や特急を利用すれば21分の距離に岐阜駅はある。そこから、北に300メートル。洒落た居酒屋や、小粋なセレクト・ショップの集まるタマミヤ商店街の端っこに、広中美桜と大夏の実家である喫茶『甍』はあった。二年前、母の琴子に、認知症の初期という診断が出て店は閉じたが、今も、一階の内装は営業当時のままだ。
「こっちに帰ってきて欲しいんだよ。母さんのために」
二年前、弟の大夏から、電話がかかってきた。
「姉ちゃん。俺、認知症の介護なんて一人じゃ絶対無理。だから、錦の部屋は引き払って岐阜に帰ってきてよ。頼むよ。姉弟仲良く、介護は半分半分で頑張ろうよ」
美桜は、その日のうちに錦のクラブを辞め、岐阜に戻った。
翌日、大夏は、美桜にこう言った。
「俺、姉ちゃんと違って、男じゃん? そろそろ家を出て、男として、大きな勝負ってやつをしてみたいんだけど」
「は? ふざけんな!」
美桜は、カフェ用のテーブルを蹴り飛ばした。
「や、俺だって母ちゃんのことは考えてるよ? でも、今働いてる店の店長がいきなり中学の時の部活の後輩に変わっちゃって、なのに俺はずっとバイトのままで、その後輩が俺に、職場ではちゃんと自分に敬語を使えって言いやがって……うわ!」
美桜は、大夏の言い訳に、渾身の右ストレートで応えた。が、怒りで肩に力が入り過ぎ、大夏の顔面にはクリーン・ヒットしなかった。
「何逃げてんだ、テメエ! 避けるな! ちゃんと顔の真ん中で受け止めろ!」
「無茶苦茶言うなよ! そんなパンチ、顔の真ん中で受けたら鼻が折れるよ!」
「それで良いんだよ」
「はあ? 何が良いんだよ!」
「おまえみたいなクソ男はな、一度きちんと痛い目に遭わないとダメなんだよ。だから私が、姉の責任としておまえを今ここで半殺しにする。グタグタ言ってっと、素手じゃなくて木刀持ち出すぞコラッ!」
大夏は逃げた。自分の携帯電話だけ握り締め、家から岐阜駅まで走り、電車に飛び乗って名古屋まで逃げた。以来、美桜は常にこう言っている。
「あいつはもう、弟じゃない。未来永劫、家族なんかじゃない」
にもかかわらず、広中家ではここ数日、リビングから繰り返し、その「元・弟」の声が大音量で再生されていた。
「広中大夏です。28歳です! ダンスは初心者ですが、俺、死ぬ気で練習します!」
「広中大夏です。28歳です! ダンスは初心者ですが、俺、死ぬ気で練習します!」
「広中大夏です。28歳です! ダンスは初心者ですが、俺、死ぬ気で練習します!」
大きな木のトレイに昼食を載せ、美桜は憂鬱な気持ちでリビングに向かった。ちなみに、本日の昼食は『鶏ちゃん』。タレに漬け込んだ鶏肉を、キャベツ、人参、玉ねぎと一緒に焼いたシンプルな料理だ。これを、琴子は今日で四日連続、美桜にリクエストしている。
リビングに入る。
テレビ画面には、とある情報番組の映像。胸に大きなゼッケンを付けた大夏が画面の真ん中に映っていて、琴子がそれをうっとりとした表情で眺めている。ちなみに今月、琴子はずっと、オレンジ色の麦わら帽子にオレンジ色のTシャツ、そしてオレンジ色のスカートを履いている。今日もそうだ。
「夏と言えばオレンジ色でしょ? 太陽みたいに明るくてポジティブで、大夏にぴったりの色だと思うの」
そう、琴子は何度も言う。ちなみに、琴子は春の間はずっとピンク色の服を着ていた。ピンクは美桜の色だからだそうだ。
「広中大夏です。28歳です! ダンスは初心者ですが、俺、死ぬ気で練習します!」
リモコンで再生を止め、琴子はまた数秒だけ巻き戻す。
「お母さん、ご飯よ? テレビは消して」
「でも、大夏がテレビのニュースに出てるのよ。ご飯なんか食べてる場合じゃないでしょ?」
「なんでよ。録画なんだから、ご飯食べてからまた見れば良いでしょ?」
「それじゃあ、ダメよ」
「なんでよ」
「ご飯の後にしたら、美桜ちゃん、どっか行っちゃうでしょう? 私は美桜ちゃんと一緒に続きを見たくて、ずっと最初の部分で止めてるんだから」
「まじか」
琴子がまた再生ボタンを押す。
「広中大夏です。28歳です! ダンスは初心者ですが、俺、死ぬ気で練習します! あと、俺、女子大小路でバーテンダーやってます! 是非飲みに来てください! 女子大小路は、どまつりの会場のすぐ近くです!」
審査員席にいる女優がアップで映る。水田智秋。人気女優だ。彼女はマイクを手に取り、わざわざ大夏に質問をする。
「そのお店は、何ていうお名前ですか?」
「タペンスって言います! 池田公園のすぐそりゃれありゅます」
大夏が緊張で言葉を噛み、会場にいた全員が大声で笑う。それを見て、琴子も大笑いをする。
美桜は、琴子の手からリモコンを取り、テレビごと電源からオフにした。
「あら、美桜ちゃんったら」
琴子が口を尖らすが、その昔、「食事中はテレビ禁止」というルールを広中家に持ち込んだのは琴子である。
「さあさあ、冷めないうちに食べよ。いただきます」
美桜が、鶏ちゃんに手を合わせ、琴子も同じように手を合わせた。
「大夏のニュース、あと10回は観たいわ」
琴子が、鶏ちゃんを大口で頬張りながら言う。
「本当にあいつは、広中家の恥晒しだよね」
そう美桜が言い返す。
「あの子ったら、いくつになっても可愛い女の子の前だとあがっちゃうのね。なんて可愛いのかしら。そういうところ、パパにそっくり♡」
口の中に鶏ちゃんを入れたまま、琴子は「うふふ」と笑う。
「弟の話は嫌だし、うちらを捨てて出てった男の話はもっと嫌」
美桜がまた冷たく言い返す。
「やだわ、美桜ちゃん。そんな……捨てただなんて」
琴子が、両手を頬に当てて抗議をする。
「捨てたでしょ? フィリピンパブの女の方を選んで、私らを捨てたでしょ?」
少し肩をすくめて、美桜は言う。
「それはそうだけど、でもでも、それだって、悪いことばかりじゃないでしょう?」
「は? どこが? 父親が家族を捨てて他の女と駆け落ちすることに、どんな良い部分があるの?」
「それはほら。これから頑張るのよ」
「はあ? 誰が、何を、頑張るの?」
と、琴子は箸をトレイに置き、背筋を伸ばして美桜に向き直った。
「美桜ちゃん、私はこう思うの。『未来に何をするかで、過去の価値は変わるのだ』」
美桜も自分の箸を持つ手を止め、疑わしそうな眼差しで琴子を見つめた。
「……お母さん、また何かの受け売り?」
「ギクッ」
琴子はその擬音を声に出して言った。
「ギクッ?」
「ううん。あのね、美桜ちゃん。実は、ええと、セミナー? じゃなくて、勉強会? じゃなくて、やっぱりセミナー?とかいうのに誘われて、お母さん、この前行ってきたの。ええとええと、アドラー哲学?」
「お母さん! それ、けっこう高いお金取られたんじゃないの?」
「ううん、大丈夫。まだ、体験入会だから」
言いながら、琴子がVサインをする。
(どこからが、認知症の影響で、どこまでが、元々のお母さんの性格だったんだろう)
美桜は内心、そんなことを考える。琴子は改めて箸を手に取り、美味しそうに鶏ちゃんを口に放り込む。そして、
「でも、良い言葉だと思わない?『未来に何をするかで、過去の価値は変わるのだ』」
と言った。
「じゃ、未来に何をしたら、父親の駆け落ちに価値が出るの?」
美桜が質問をする。言ってから、少し意地悪な質問だとは思った。琴子は、それには何も言わなかった。聞こえなかった、という演技をしているように美桜には見えた。
19年前。昼。
喫茶『甍』は、通常営業をしていた。
美桜は、大夏と一緒にタマミヤ商店街に買い物に出かけた。あんかけパスタのための野菜と玉子とウインナーを買い足しに。
大夏は美桜の横でずっと、アホみたいに踊っていた。
店に戻ると、大夏は店内でも踊った。
それを見て、客のおじさんの一人が言った。
「坊主。もしかして、あれに出るのか? ほら、あれ。なんだっけ。真ん中がどうしたとかいう……」
「それ! どまつり! にっぽんど真ん中祭り!」
大夏は、踊りながら答えた。
「だって、リーダーが父ちゃんなんだぜ? 出るに決まってるじゃん!」
「だからって、お店の中で練習するのはダメよ?」
そう、琴子が大夏を嗜める。
「だって、父ちゃんが、ちょっとの時間でも練習しとけよって」
「だったら、店の外でやってちょうだい」
「外で踊ってたら、姉ちゃんに殴られた」
大夏が口を尖らせて言い、そんな大夏を美桜は小突いた。
「だって、歩いてる人にバンバンぶつかってるんだよ? 迷惑でしょ!」
と、その時だった。店の電話が鳴った。琴子は、ちょうどお盆にコーヒーを載せて運んでいたので、両手が塞がっていた。
「美桜。押して」
琴子に言われ、美桜は、電話機のオンフック・ボタンを押した。
「はい、喫茶『甍』でございます」
琴子が大きな声で応対する。
「母さん。仕事中、ごめんね」
父の声だった。その声は店じゅうに丸聞こえだったが、琴子はまるで気にせず、
「あら、お父さん。どうしたの?」
と、華やいだ声を出した。
「美桜と大夏は、もう帰ってるかい?」
「ええ。ここに一緒にいるわよ?」
「そうか。じゃあ、三人とも良く聞いてくれ」
なんとなく、いつもの父とは声の雰囲気が違っていた。大夏が、踊るのをやめた。店には客が二組。常連の近所のおじさんとおじさんとおじさん。それと、初めて見る若い男の一人客だった。客も全員、父の言葉を聞いていた。
「実はな……」
声が、少しだけ上ずる。これから良くない話をするのだ。それが、まだ子供だった美桜にも察せられた。
「お父さん、フィリピン・パブの女性を好きになってしまったんだ」
「!」
店じゅうが、とても微妙な空気になった。
「これから、彼女と駆け落ちをする。だから、琴子、美桜、大夏……みんな、父さんのことは忘れてくれ。ごめん。じゃ」
そして、電話は切れた。
父さんのことは忘れてくれ。
ごめん。
じゃ。
なんて簡単な言葉。
父さんのことは忘れてくれ。
ごめん。
じゃ。
なんて簡単な、家族の終わり。
と、琴子が美桜と大夏の方に振り返った。
「オホホホ。お父さんったら何を言っちゃってるのかしら。お父さんにしては、珍しくつまらない冗談ね?」
同意を求めるように、琴子はふたりの子供に言った。
「お父さんの冗談が面白い時ってあったっけ?」
大夏が言う。
「そう? お母さんは、お父さんの冗談、好きよ?」
琴子が明るく言う。
「でも、今のはあんまり面白くなかったわね」
美桜が言う。
「そうね。でもまあ、良いじゃない。冗談は冗談なんだから」
そう、琴子が話を締め括る。
しかし、全然良くはなかった。あの電話は、冗談ではなかった。あれから19年。父は今、どうしているのだろう。生きているのか。死んでいるのか。もしも願いが叶うなら、ぜひ、そのフィリピン人のホステスに貢いだ挙句に捨てられ、どこかで野垂れ死にしていて欲しい。