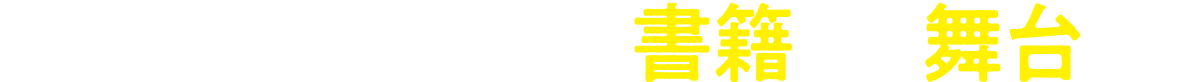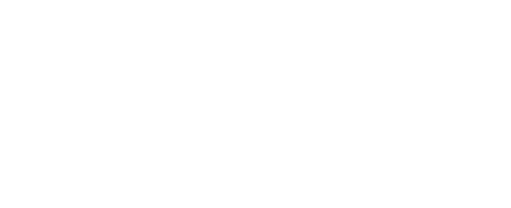書式設定
- 文字サイズ
-
- 小
- 中
- 大
- 特大
- 背景色
-
- 白
- 生成り
- フォント
-
- 明朝
- ゴシック
- 組み方向
-
- 横組み
- 縦組み
書式設定
「第3回」
化粧気のない顔に、白いTシャツとクラッシュ・ジーンズ。それでも智秋の姿は、大夏には、 華やかな舞台衣装を身に纏った主演女優の登場シーンに見えた。
「あの」
ドアの前で智秋が言う。
「は、はひ……」
大夏は声が裏返った。
「もしかして、お店、開店前でした?」
その瞬間、大夏は文字通り飛び上がった。
「いえ! すみません! 開店してます! この店、早めの時間はいつもガラガラでして、それでその、お客さんいないならダンスの練習してた方が有意義かなとか、ほら自分、『死ぬ気で踊ります』ってオーディションで言ったし、それ、絶対嘘にしたくないし、智秋ちゃんの主演映画、絶対映画にしたいし!」
すると、智秋はなぜか寂しげに微笑み、大夏を見つめた。
「広中、大夏さん……でしたよね?」
「はい」
「そんな風に思ってくださって、ありがとうございます」
スッと智秋が頭を下げる。意味がわからない。日本を代表するような美人女優が、自分に「ありがとうございます」と言う。大夏の鼓動が1分あたり180を超えた。智秋は顔を上げると、今度は明るく、
「じゃあ、カウンター、座って良いですか?」
と言った。
「は、はい!」
大夏がスツールを引く。慣れた感じで、智秋はそこに座る。そして、店内を改めてぐるりと眺めた。
「素敵なお店ですね」
「そ、そうですか? 殺風景とか、よく言われるんですけど」
言いながら、大夏はアナログのレコードを取り出し、ターン・テーブルに載せる。すぐに、チェロの柔らかい音色が店内に流れ出す。開店したら、最初にこのレコードをかけること。大夏がこの店に雇われた時の、唯一の決まりがそれだった。
「お飲み物はどうされますか?」
智秋が、軽く肩をすくめる。
「私、実は、お酒、ダメなんですよ」
「え? そうなんですか? あ、めっちゃ薄めに作るとか、あるいは飲みやすい甘いカクテルとかもありますよ?」
「いや、お酒は強いんです。すごく」
「え?」
「それが、とっても嫌で」
「へえ……」
智秋は、小さな苦笑いを浮かべていた。
(智秋ちゃんって、いろんな種類の笑顔を持っているんだな)
大夏はますます自分の恋心が加速するのを感じた。
「なので、このお店で一番高いノンアルコールをください」
語尾の「ください」の時の微かな首の傾け方が可愛かった。狙っていないのに可愛いという、世界の可愛さの中でも最上級に絶妙な可愛さである。大夏は、地球の重力が小さくなったかと思った。このままだと、いつか夜空に飛んでいけそうだ。
と、智秋の携帯が鳴った。着信画面を見て、智秋が表情を少し曇らせた。数秒迷ってから、彼女は電話に出た。
「もしもし……あ、うん……なんで? 全然、大丈夫だよ?」
彼氏だろうか? いや、水田智秋には彼氏はいないはずだ。以前、ネット・ニュースにそう書いてあった。では、電話の相手は誰だろう。タメ口なので、仕事以外の友人だろうか。
「待ってよ。そのことは、あの時にちゃんと話し合って納得してくれたよね? それに、これは私の問題でもあるんだよ?」
少しだけ、智秋の声が大きくなった。そして、身を固くしている大夏の様子に気がついたようだ。智秋は電話の相手に、
「ごめん。今、ちょっと私、人と一緒なの。また後でかけ直すね」
と言って、切った。
「あ、や、全然遠慮なく。今はタペンス、智秋ちゃんの貸し切りなんで」
(どうぞ、どうぞ)という身振りを加えながら大夏は言ったが、智秋はその日一番の明るい笑顔で、こう答えた。
「良いんです。今日は、仕事のことは忘れて、楽しく飲みたい気分なんで」
大夏の鼓動が、再び、1分あたり180を超えた。それを必死に深呼吸をして抑える。それから、よく通る声と滑舌を意識しながら、大夏は智秋に言った。
「あ、お腹、空いてませんか? 俺、作りますよ。俺、こう見えて、お酒作るより料理の方が得意なんです。実は、実家が喫茶店やってて、でも、俺の母ちゃん、実は料理が下手で、父ちゃんは料理めちゃ上手いんですけど、実は別の仕事もやってたんで、で、なんだかんだ、俺、小さい時から、喫茶店のランチとか軽食とか、家事手伝いでガンガン作ってたんですよ」
どことなく頭が悪そうな喋り方になってしまったが、智秋は気にしていないようだった。
「へええ。喫茶店を」
そう、店内のあちこちを見ながら返答してくれる。
「はい。岐阜のタマミヤってとこで」
「へええ」
興味がある「へええ」なのか、無い「へええ」なのか、智秋の受け答えはちょっと掴みどころがなかった。そして大夏は、そういうミステリアスな女性に弱かった。しばらく智秋は何かを考えていたが、やがて、
「大夏さんのご実家のカフェで、一番、人気のあったメニューってなんですか?」
と質問してきた。
「あー、なんだろう。あれかな。あんかけパスタ」
「あんかけパスタ」
「名古屋では、あんかけスパって言う方が多いんですけど、うちではパスタって言ってましたね。レシピ、父ちゃん。作るの、俺。で、姉ちゃんが、最後にちょっと辛味を足してドヤ顔するのがお決まりでした」
「じゃ、それで」
「え?」
「私、そのあんかけパスタが食べたいです」
そこで、大夏は戦慄した。何でも作れるとは言ったものの、背後の冷蔵庫の中は確認していなかった。引き攣った笑顔のまま素早く身を反転させ、冷蔵庫のドアを開ける。玉ねぎは有る。ピーマンも有る。ベーコンは無いけれどウインナーは有る。いや、違う。問題は冷蔵庫の方ではない。その横の戸棚を開ける。やはりだ。無い。片栗粉が無い。あれが無ければ、肝心のとろみが付かない。
「智秋ちゃん。ちょっとだけ、留守番していてもらって良いですか? すぐ戻るんで」
「え?」
「本当に、すぐ、戻りますから!」
雪乃の小料理屋になら、片栗粉は有るだろう。万が一無かったら、その先のスーパーまでダッシュあるのみだ。そんなことを考えながら、大夏は店の外に出て、薄暗い階段を三段飛ばしで駆け下りた。と、最初の踊り場を回ったところに、黒い大きな塊がいた。人間だった。男だ。夜でも熱中症になるかもしれないという真夏の名古屋で、その男は黒のジャージの上下に黒いキャップ、更に黒いマスクまでしていた。そして……
(ほ、包丁?)
大夏は息を呑んだ。男は手に、剥き出しの刃物を持っていたのだ。と、次の瞬間、男はそのナイフを振り上げ、大夏に向かって斬りつけて来た。
「ぶひゃへぅ」
言葉にならない悲鳴を上げながら、大夏は身を捩った。頬すれすれを刃物が通過する。
尻もちをつく。そのまま四つん這いで階段を上がる選択を大夏はした。タペンスに飛び込み中から鍵を掛け、それから警察に通報だ。そう考えた。が、出来なかった。階段を二段上がると同時に、右の尻に激痛が走ったからだ。
「ギュワ」
変な声が出た。焼けるような痛みだった。と、大夏の視線の先、タペンスのドアが開いて智秋が顔を出した。
「大夏さん?」
と、次の瞬間、黒づくめの男は大夏を飛び越え、智秋に向かって突進を始めた。大夏は、自分の顔面の上を通過しようとした男の足にむしゃぶりつき、自分ごと、男を階段の踊り場に引き摺り下ろした。
「智秋ちゃん! 出てきちゃダメだ! 鍵をかけてから110番……」
そう叫ぶのと、男の右肘が側頭部に飛んでくるのが同時だった。衝撃で、目の前に星が飛ぶ。男は体勢を立て直すと、うずくまっている大夏の身体を、更に下の踊り場に向かって容赦なく突き落とした。
6
名古屋市の北西部にあたる中村区。岐阜の池田山から車で一時間半。望月は桜色のホイールを装着した愛車を、名古屋高速都心環状線から六番北インターチェンジ、名古屋高速4号東海線、国道1号、そして昭和橋を左折して中川運河西線へと走らせた。道の両脇に大型のトラックが多数停車している倉庫街の奥、一度右折をした先の突き当りに、大夏が搬送された名古屋掖済会病院は在る。大小の白いマッチ箱を組み合わせたような外観。望月号が現地に到着をした時、時刻は夜の11時になっていた。『救急外来入り口』の青い看板の前に、緒賀冬巳が待っていた。黒いスーツ越しでも明確にわかる筋肉質な身体。エントランスの非常灯が、彼の困惑したような表情を照らしていた。美桜は、助手席から素早く降りたが、それよりも、運転席の窓を開けて望月が怒鳴る方が早かった。
「緒賀ァ! このセクハラ刑事が! 開示請求するぞ、コラァ!」
「は?」
いきなり怒鳴られた緒賀が気色ばんだ。が、望月はまったく動じない。
「テメエが担当してた事件はもう終わったろ! なんで、美桜ちゃんの連絡先勝手に残してんだコラ! 公務員職権濫用罪で訴えてやる!」
「そんなことより、なぜ白豚弁護士が一緒に? 広中大夏くんは今回は容疑者じゃなくて被害者なんですが」
「弁護士にその口の利き方はなんだ、平刑事!」
「そっちこそ深夜の病院で何大声出してんだ、豚野郎。俺の正拳突きが見たいのか?」
「こ、今度は脅迫罪だ!」
言いながら、望月が車を降りて緒賀に詰め寄る。車椅子の老人が、看護師に連れられるように、通り掛かった。緒賀も望月もエントランスの真ん中で言い合いをしているので、通行の迷惑であることは明白だった。望月の車も放置されたままだ。
「道を開けろ、二人とも。おじいさんの邪魔だろうが」
美桜が殺気を孕んだ低い声で命じると、緒賀と望月は素直に左右に分かれた。看護師がふたりをじろりと睨め付けながら、車椅子の老人と共に通過した。
「で、緒賀さん、大夏の病室は?」
「303です。あ、ただですね。大夏くん実は……」
「病室だけで結構です。緒賀さんも、望月先生も、今夜はどうかお引き取りを」
そう言って、美桜はひとり、病院の中に入った。夜間灯に仄白く照らされた廊下を進み、階段で三階まで上がる。再び廊下を進み、ナース・ステーションを素通りして、『303号室』と印字されたドアの前に立った。意識不明、という単語が、思い出された。ドアを開けるのに、少しだけ勇気が必要だった。
「あなたはお姉ちゃんなんだから、大夏のこと、これからもお願いね」
母の琴子が、懇願するように美桜に言ったことを思い出した。父が家を出てから、やたらと琴子から大夏のことをお願いされるようになったのだ。
(なら、私のことは誰がお願いしてくれるのだろう)
その都度、そんなことを思ったが、口には出さなかった。そういえば、父がまだ家にいた時も、似たようなことを言われたことがあった。
「もしも父さんに何かあったら、美桜が母さんと大夏を守っておくれ」
今更だが、とても腹立たしい言い草だ。何かあったらというのは、普通、事故とか病気だろう。自分の意思で別の女と駆け落ちすることではないはずだ。
怒りを思い出すことで、ドアノブを回す力が生まれた。
ガチャリ。
やや、乱暴にドアを開ける。
クリーム色のカーテンが下がる腰高窓。小さなシンクの付いた洗面台。細長いロッカーと背の低い床頭台に、パイプ椅子が一つ。そして、その奥にベッド。大夏らしきシルエットが、妙な形で横たわっている。頭部に白い包帯。腕に点滴。片足にギブス。死んでいるわけではないようだ。ゆっくりと美桜は病室に入る。シルエットの違和感の理由はすぐにわかった。大夏はうつ伏せの状態で寝かされていたのだ。パジャマの下を履いておらず、尻全体を覆うように包帯が巻かれ、その上からふんどしのようなもの(T字帯というらしい)が当てられている。
「大夏……」
美桜は、声をかけながら、体を屈めて大夏の顔を覗き込んだ。そして、ギョッとした。彼女の弟は、目を瞑ったまま、微笑んでいた。
「大夏?」
「いやん♡」
「? いやん?」
枕の上で、大夏の表情がだらしなく動く。どうやら、夢を見ているようだ。意識不明の重体ではなかったのか?
「大夏」
少し強めの声で呼んでみた。
「……」
「大夏!」
「なんだよー、ち・あ・き♡」
「大夏!!」
言いながら、包帯が巻かれた大夏の尻を、美桜は思い切り叩いた。
「! 痛ッ! 痛ッた! って、あれ? 姉ちゃん?」
大夏が、驚いたように目を見開いた。
「貴様。意識不明はどうした?」
「え? 何のこと?」
「意識不明の重体じゃなかったのか?」
「あー、うん。そうだったみたい。階段から落ちた時に頭を打って、ちょっと脳震盪で」
「は? 脳震盪と意識不明は違うだろ?」
「知らないよ。つか、なんで姉ちゃんなんだよ。俺、今、これまでの人生で最高にハッピーな夢を見てたのに! バカ! ぐはっ!」
グルグル巻きになっている尻に美桜が右肘を落とすと、大夏は悶絶した。いつの間にか病室のドアのところに緒賀が来ていた。
「美桜さん。大夏くんは、尻を包丁で刺されてるんです」
そう緒賀は言ったが、美桜は気にしなかった。
「脳震盪を起こしたってだけで、私を岐阜から呼び出したんですか?」
じろりと緒賀を睨むと、彼は気まずそうに少し下を向いた。
「や、それだけでなく、階段から蹴り落とされて足も骨折しています」
「骨折? そんなの、普通に暮らしてても骨折くらいはしますよね?」
「や、その、自分が美桜さんにお電話をした時には、まだ怪我の詳細も分かっておりませんでしたし、大夏くんの意識もありませんでしたし、それにその、電話を切ったすぐ後に大夏くんの意識は戻りましてその後はとてもピンピンされていたのですが、状況的には殺人未遂事件と言えるくらいの凶悪犯罪でしたし、そう言う場合は警察からご家族には連絡をしなければいけないことに……」
珍しく、緒賀の言葉はしどろもどろだった。それを最後まで聞かず、美桜は病室を出た。
「姉ちゃん?」
「美桜さん?」
大夏と緒賀の言葉は同時だった。美桜は振り返ると、緒賀にだけ言った。
「以前にも言いましたが、そこのバカ男とはもう家族の縁を切っているんです。心臓を刺されたとか、頸動脈を切られたとかならまだしも、尻を刺されたくらいでいちいち電話して来ないでください」
廊下には、望月がいた。美桜が緒賀に怒っているのが嬉しいらしく、犬が尻尾を振って喜びを表現するように、望月は大きな尻を左右に振って喜びを表現していた。
「じゃあ、美桜ちゃん。また岐阜まで送るよ」
揉み手をしながら提案をしてくる望月。
「いえ、結構です」
「でも」
「望月先生、今夜は本当にありがとうございました。先生のご自宅は名古屋ですよね? まだぎりぎり終電も間に合いますし、私は電車で帰ります」
「そんなこと言わないでよ。岐阜まで送らせてよ」
「望月先生」
「はい」
「それ以上しつこくすると、私、キレますよ?」
「え……」
望月は、実は臨機応変なタイプだった。そして、めげない男だった。
「じゃあ、せめて、名古屋駅まで送らせて♡」
その時、病院の外に、ひとりの男がいた。黒いキャップを被った男だった。男は近隣のビルの陰から、救急外来のエントランスをずっと見つめていた。
やがて、エントランスに広中美桜が現れた。色白の太った男と何か会話をしていたが、結局その男を置き去りにし、彼女はひとりで夜道を歩き始めた。
男は、帽子を目深に被り直した。
そして、彼女の跡をつけ始めた。
7
「あー! もうダメ!」
そう叫ぶと、稲熊彩華は、ダンゴムシのように体を丸めた。
久屋大通り沿い。栄駅から矢場町駅の中間くらいにある「にっぽんど真ん中祭り文化財団」の会議室。もう夜の9時になるというのに、会議室にはまだ大勢の学生たちが残っていた。どまつり開催まで、一週間を切っていて、 やるべき事はまだ山のように残っている。
どまつりの大きな特徴のひとつに「運営は学生主体」というルールがある。25名の「学生委員会」。そして、学生ボランティアが約700人。稲熊彩華は、この大人数を束ねる委員長だ。
「彩華ー、どしたー?」
向いの長机でパソコンに向かっていたMC班班長の杉下奈緒が、画面から顔も上げずに聞いてくる。その横にいる舞台班班長の坂田和樹が、
「大丈夫だって、稲熊。何のことか知らないけど、多分、どうにかなるって」
と、のんびりした声を出す。
彩華は自分のパソコンの上で、頭を左右に激しく振る。
「だってさ。毎年毎年準備ギリギリなのに、今年は映画とのタイアップまであるんだよ? 予告編の映像撮りたいから、去年の上位チームのリハ風景撮らせろとか今頃になって言ってくるんだよ? それをさ、勝手に水野さんとかOKしちゃってさ、『対応よろしく』って一言で段取りは全部こっちに丸投げだよ? どゆこと?」
水野さんというのは、どまつり文化財団を立ち上げた水野孝一専務理事のことだ。
「映画のために、このクッソ暑い炎天下で、みんなに余計に何回も踊ってもらうの? 熱中症対策はどうするの? 万が一、体調不良の人が出た時の対応は? ドローン撮影の許可取りは? 野次馬対策は? どまつりまであと一週間無いんだよ?」
言えば言うほど感情が昂り、彩華は目頭が熱くなってくるのを感じた。
「うん、わかるよ。彩華の気持ちはよーくわかる」
カタカタと、ファイナル当日の進行表を修正しながら、奈緒は言う。
「水野さんには、私たち全員に『うな藤』の特上ひつまぶし税込6700円をご馳走してもらおう。どまつり終わったら、私が責任持って水野さんに交渉する。だから今は、もう少しだけ頑張ろ? ね?」
奈緒は、いつも冷静だ。おまけに、スタイルも良く顔も可愛い方だ。
「奈緒が委員長やってた方が、絶対、いろいろスムースだったよね。どうして私がなっちゃったんだろう」
彩華が愚痴ると、和樹が「ハハッ」と声を上げて笑った。
「何よ」
「や、別に。今、一番無駄な後悔だなと思って」
「悪かったわね」
「や、別に悪くはないよ。ただ、まあ、無駄だよなと思って。ハハッ」
「……」
無駄な愚痴を言っていることは、自分が一番判っている。何も言い返す言葉が見つからず、彩華はただ、グッと唇を噛み締めた。と、会議室のドアが開き、運営班の須藤太一が入ってきた。
「おつ。なーんか、嫌な雰囲気だよね」
入ってくるなり太一が言う。
「嫌な雰囲気にしてごめんなさいね」
「ん?」
「耳、悪いの? 嫌な雰囲気にしてごめんなさいねって言ったの。謝ったの」
彩華が、逆ギレの気持ちを隠さずに言うと、太一はキョトンとした表情で、
「委員長のことじゃないよ。チーム・オトナのことだよ。今さ、水野さん、すっごい難しい顔で誰かとヒソヒソやってたよ」
と言い、わざとらしく眉間に皺を寄せた。
「水野さんが? 誰と?」
「相手はわかんない。でもあれ、かなり深刻なトラブルの時の表情だよ。やっぱ、あの噂、マジなのかな……」
「何? 噂って」
彩華が尋ねると、太一も和樹も奈緒も、全員が「え?」と同時に驚いた。
「委員長、知らないの?」
「知らない。だって、ここんとこずっと鬼忙しかったかし。あー、でもでも言わないで。私には何にも言わないで」
そう言って、彩華は両手を顔の前でぶんぶんと強く振った。噂話は人並みに好きだ。でもそれは、それなりに心と時間に余裕のある時の話だ。今、そんなことに、限りある脳のリソースを割く余裕は無い。どまつり本番まで、残り一週間も無いのだ。
「でも、内容的には委員長も知っておいた方が良いんじゃないかなあ」
太一が言う。とっても話したそうだ。が、ちょうどその時、彩華の携帯が鳴った。
「お。彼氏? 束縛強めの」
和樹が茶化す。
「そいつとはとっくに別れました」
「そうなの?」
「はい。私から、振りました」
語気強めにそう説明しながら、彩華は携帯を手に取る。着信画面には「大家さん」と表示されていた。
「え? なんで?」
通話ボタンを押すと、スピーカー・ボタンをオンにしたかのような、大家の老人の大声が会議室内に響いた。
「おい。今すぐ病院に来てくれ?」
「は?」
この大家は、彩華のことを名字でも名前でも呼ばない。いつも「おい」だ。ちなみに、大家と彩華は血の繋がった祖父と孫……などという関係ではなく、単に家賃で繋がっているだけの大家と賃借人だ。「おい」呼びは失礼極まりない。ただ、家賃は安い。西川端通沿いという立地考えると、古い木造マンションであっても相場の2割近く安い。
「病院だ。頼みたいことがあるんだ」
「ちょっと待ってください。無理ですよ」
「急ぎなんだ! 早く来い!」
なぜ、命令形で言われなければならないのか。いくら家賃が安いからといって。
「そんなこと、急に言われても無理です! もうすぐ『どまつり』なんですから!」
そう叫んで携帯を切ろうとしたが、大家の老人はそこにこんな言葉を被せてきた。
「家賃、タダにする!」
「へ?」
気がつくと、会議室にいる全員、仕事の手を止めて彩華と大家のやり取りを見守っている。
「今すぐ病院に来てくれれば、来月分の家賃はタダにする。これは、俺の人生を賭けた問題なんだ」
まだ丁寧語ですら無いけれど、この大家にしては、少し頭を垂れた雰囲気の声が続いた。
「いや、でも……」
彩華が口ごもる。
「なら、家賃、二か月分タダにする」
「え」
「俺も生活があるからずっとタダって訳にはいかんが、今すぐ病院に来てくれれば、二ヶ月分の家賃をタダにする」
「……」
いつの間にか、奈緒が彩華の横に来ていた。ポンポンと彩華の肩を叩き、そして耳元に小声で、
「行っておいでよ」
と囁いてきた。
「どまつりの準備で、バイトだってあんまり出来てないでしょう? どんな用事か知らないけど、ここはフットワーク軽く行って来たら? 私で代われる仕事ならやっておくし」
「奈緒……」
「その代わり、明日はスタバのストロベリー・フラペチーノを奢りで」
「あ、それなら俺は、ダークモカチップ・フラペチーノ!」
これは和樹。
「それ、ふたつで」
これは太一。
「おい! 早くしろ! 名古屋掖済会病院だ! 病院に入らず、200メートル手前から俺に電話しろ! わかったな!」
言いたいだけ言って、大家は一方的に電話を切った。本当に腹立たしい大家だ。一体、どういう用件なのだろう。でも、アパートの家賃が二ヶ月分浮くのは大きい。
5分後。彩華はどまつりの事務所を出た。Googleマップで、名古屋掖済会病院への経路を検索する。距離10㎞。遠回りになる電車より、自転車の方が早い。Googleの予想では35分。お気に入りの白のクロスバイクは、ビルの裏手に停めてある。ノート・パソコンと資料でパンパンのリュックを背負い、携帯のストラップを肩から斜め掛けにする。二つ掛けにしているチェーン・キーを外し、夜の街に向かってペダルをグイッと踏み込んだ。三蔵通り。そして国道一号線。名古屋の夏は、夜でも酷暑だ。今夜も、21時を過ぎて気温はまだ30度以上だ。漕ぐ。熱風を壁のように感じながら漕ぐ。まるでサウナ・ヨガだ。数分で全身が汗まみれになる。でも、この暑さの中、どまつり参加チームのみんなは踊るのだ。全身全霊で踊るのだ。なのに、委員長である私が泣き言を言っていてどうする。そんなことを考える。
自分も踊り子だった高校時代。
裏方ボランティアの楽しさに目覚めた大学一年生。
自分のアイデアをミーティングで言えるようになった大学二年生。
初めて出来た彼氏を振ってまで、どまつりに集中し続けた大学三年生。
昭和橋を渡って右に。明りの消えた倉庫街を、フル・スピードでひたすら走る。遠くに名古屋掖済会病院が見えてきた。大家に電話をするため、彩華はクロスバイクを道の端に停めた。
と。
正面から、女性がひとり、歩いて来た。暗い夜道に、そこだけスポットライトが当たっているかのように見えるほどの美人だった。大きな瞳。スッと通った鼻筋。程良くセクシーな唇。ランウェイを歩くモデルのような美しい歩き姿。ただ、彼女の表情は厳しい。何かに強く怒っているようだ。じっと観察している彩華の視線を気にもせず、その女性は彩華のすぐ横を通り過ぎた。その時、彼女の独り言が彩華にも聞き取れた。
「あのクソボケ。いつか殺してやる」
美人は、そう吐き捨てるように言っていた。彩華は魅入られたように、去っていくその女の後ろ姿を見つめていた。すると、斜め掛けにしていた携帯がブルブルと震えた。大家からだった。
「もしもし。今、掛けようと思ってたところなんですけど」
「もう遅い。このノロマが」
「え?」
「もう遅いんだよ。もう来なくて良い」
「ど、どういうことですか?」
「どうもこうも、もうあいつはどっか行っちまっったんだよ! この役立たず! 家賃、遅れたら追い出すからな!」
大家の老人は、一方的に喚き、一方的に電話を切った。全く意味がわからない。一体、これは何なのか。一体、自分の身に何が起きたのか。あいつとは誰だ。大家は私に何をさせたかったのか。汗まみれの身体のまま、彩華は道端にしゃがみ込んだ。
(やばい。私、泣くかも)
そんなことを思う。
と、通りすがりの男性がひとり、彩華に声をかけてきた。
「大丈夫ですか? 何か、お困りですか?」
「え?」
細身の中年の男性だった。街灯が逆光になっていて、顔は良く見えなかった。
「大丈夫です。あんまり今日も暑いから、ちょっと休憩してただけです」
そう彩華が答えると、男は自分のリュックを背中から前に回し、中から拳大のものを一つ、取り出した。
「これ、夏バテに良く効きますよ。良かったら食べてください」
そう言って、彩華の手に野菜を一つ握らせ、男は去って行った。
「あ……ありがとうございます……」
戸惑いつつも、お礼を言う彩華。彼女の手の中に残ったのは、大きくて形の良い玉ねぎだった。
8
二日後。愛知県警中警察署の大会議室では、「どまつり関係者連続傷害事件」の、第一回合同捜査会議が開かれた。それまでは、被害者が軽傷だったこともあり事件現場の所轄署で個別に捜査が行われていたのだが、広中大夏の事件で凶器が刃物にエスカレートしたことと、どまつりの実行委員会に脅迫状が届いたことで、県警は捜査本部の設立を決断したのだった。
緒賀と、緒賀の相棒の鶴松刑事は、前から二列目の窓際の席に座っていた。
捜査資料をパラパラとめくっている緒賀に、
「この前教えたお店はどうでした?」
と、鶴松が訊ねてきた。緒賀は、東京警視庁から人材交流で来たいわゆる「他所者」であり、鶴松はそんな緒賀のために、「オフの日にはここに行くべし」という名古屋飯激ウマいリストを作成しては彼に渡していた。
「行ったよ。驚いた。あんかけスパゲティの上に、エビフライが3本も乗ってたよ」
「豪華だったでしょ」
「いや、ちょっとトゥー・マッチな感じがした」
「いやいや、ちょっとやり過ぎるところも名古屋テイストなんですよ」
「そうなのか?」
「そうなのです。緒賀さん、まだまだですね」
会議室に、三枝本部長と樋口係長が入ってきた。あちこちから聞こえていた私語が一斉に止む。正面の長机に座るや、三枝はすぐにマイクを手に話しを始めた。
「どまつりの実行委員会宛に、脅迫状が届いた」
三枝はいきなり本題に入った。大会議室の空気がピンと張り詰めた。三枝は、一通の封書を取り出すと、そのままそれを読み始めた。
「にっぽんど真ん中祭りの実行委員会に告ぐ。私は、どまつりと、どまつりに関わるすべての人間を深く憎む者である。今年のどまつりを中止せよ。中止の決定がなされるまで、私は、どまつり関係者を無差別に襲撃する」
静寂。
三枝は、数秒空けて、もう一度、脅迫状を読み上げた。それから、封書をポンと長机の上に放ると、捜査員たちに向き直った。
「ところで、刑事諸君。君たちは『にっぽんど真ん中祭り』の経済効果がいくらか知っているかね?」
緒賀は知らなかった。鶴松をチラリと見たが、彼も知らないようだった。
「約400億円だ」
三枝がすぐに答えを言う。
「400億。この犯人は、それを捨てろと言っているわけだ。どまつりに何の恨みがあるのかは知らないが、個人の恨みひとつで、私たちの愛する名古屋から、最高に楽しい祭りと400億円を奪おうとしている。それも、無差別連続傷害事件という、最も卑劣な手段を用いてだ。諸君は、こんなことが許されて良いと思うかね?」
静寂。三枝はまた、数秒の余白を大会議室に作った。それから静かに、
「速やかなる犯人逮捕を諸君らにお願いする。私からは以上だ」
と言って着席した。
係長の樋口がすぐに立ち上がった。
「では、合同捜査本部発足にあたり、現在までの事件について情報の確認と共有を行いたいと思います」
発表は事件の発生順である。会議室の入口側に座っていた、痩せぎすの捜査員がまず話しを始めた。
「名東警察署刑事課の青木です。私から、最初の事件について報告させていただきます。事件発生は、8月8日の20時20分頃。被害者は平井野々花さん17歳。今年のどまつりに、ダンサーとしてエントリー中です」
会議室正面にあるプロジェクターに被害の概要が映し出され、ほぼ同時に、プリントアウトされた捜査資料が参加している刑事たちに配られ始めた。
緒賀は、すでに書かれている内容をもう一回朗読するだけの会議が嫌いだった。彼は耳の機能をオフにし、捜査資料を丹念に読んだ。
事件①
発生日時:8月8日。20時20分頃
被害者:平井野々花(ひらいののか)17歳。高校二年生。
若月高校ダンス部のチーム「疾風」に所属。「疾風」は、今年のどまつりにエントリー済み。
加害者は、おそらく男性。上下黒のジャージに黒いキャップ、黒いウレタンマスク。中肉中背。年齢不詳。
発生状況。どまつりのためのダンス練習終わりからの帰宅途中、友人と別れてひとりきりになったところを狙われた。すれ違いざまに右頬を平手打ち。そして「全治3日」と書かれた四つ折りの紙を加害者は被害者に投げつけて逃亡。
事件②
発生日時:8月10日。22時25分。
被害者:高塚紗英(たかつかさえ)26歳。会社員。
地元のダンスチーム「天真爛漫」に所属。「天真爛漫」は、今年のどまつりにエントリー済み。
加害者は、おそらく男性。上下黒のジャージに黒いキャップ、黒いウレタンマスク。中肉中背。年齢不詳。
発生状況。被害者は、名古屋市港区入船にあるファミレスでダンスのフォーメーションについてのミーティング後、友人と一緒に帰宅した。途中の民家の駐車場にて、物陰から飛び出して来た加害者に拳大の石で背中を殴られる。転倒した被害者に、加害者は「全治1週間」と書いた紙を投げつけて逃亡。友人は、その場で警察に通報。
事件③
発生日時:8月13日23時。
被害者:荒瀬加奈(あらせかな)20歳。大学三年生。
愛知県立大学の学生ダンスチーム「福輪内(ふくわうち)」に所属。「福輪内」は、今年のどまつりにエントリー済み。
加害者は、おそらく男性。上下黒のジャージに黒いキャップ、黒いウレタンマスク。中肉中背。年齢不詳。
発生状況。その日、被害者は、名古屋市東区にある名古屋市東スポーツセンターにてダンス練習に参加。終了後、ひとりで自宅アパートに帰る途中、コインパーキングに停車中の車の陰から、木刀を持った男が飛び出して来た。右腕と頭部を殴られる。現場に「全治2週間」と書かれた四つ折りの紙あり。幸い、骨折には至らなかった。
事件④
発生日時:8月15日22時。
被害者:神田結子(かんだゆうこ)。25歳。会社員。
名古屋市南区を中心に構成したダンスチーム「彩祭(さいさい)」に所属。「彩祭」は、今年のどまつりにエントリー済み。
加害者は、おそらく男性。上下黒のジャージに黒いキャップ、黒いウレタンマスク。中肉中背。年齢不詳。
発生状況。南区の笠寺公園内のミニスポーツ広場でダンスの練習後、本笠寺駅に向かう途中の公園で襲われる。凶器は、金属バットで、被害者はいきなり右足の向こう脛(ずね)を強打された。現場には「全治3週間」の紙……
不快な感情が高まり過ぎたので、緒賀はここで一度、捜査資料から顔を上げた。
被害者は全員、女性。
被害者は全員、どまつりに出場予定。
これみよがしに現場に残されている「全治○○」のメモ。これは、大量に流通しているB5サイズのマルチコピー用紙に、インクジェットプリンターで印字した物で、このメモから犯人に迫るのはおそらく無理だろう。
凶器は、素手、石、木刀、金属バットと、エスカレート。その次の事件が広中大夏の事件であり、凶器は小さな刃物だった。現場に残されたメモには「全治4週間」と印字されていた。
では、次は? 次は全治3ヶ月か? それとも殺人か? 凶器は何だ? 斧か? 日本刀か? それとも銃か?
そこで緒賀は、小さな違和感を覚えた。何かに引っかかった。だがその場で、何に違和感を感じているのかを突き詰めて考えることは出来なかった。
「では、五件目の事件について、お願いします」
そう樋口が言い、それについては緒賀と鶴松が担当しなければならなかったからだ。
(おまえがやれ)
そう目で合図すると、察し良く鶴松は立ち上がった。
「五人目の被害者は広中大夏さん、28歳。女子大小路にあるタペンスというバーのバーテンダーです。彼は、どまつり出場チームのダンサーではありませんが、実は今年のどまつりは、どまつりを題材にした映画とのタイアップが予定されておりまして、彼はその映画にエキストラ・ダンサーとして参加予定でした。なので、この被害者も、どまつり関係者と言って良いかと思われます」
と、会議室の中ほどに座っていた刑事が、質問の手を上げた。
「広中大夏というのは、今年の春の連続殺人事件の時の、あの、広中大夏ですか?」
その言い方だけで、会議室の中にいる捜査員たちは全員が理解できた。
「はい。その、広中大夏です」
鶴松が答える。
「栄と錦の裏の顔役であるヤマモトと『トモダチ』だとかいう……」
質問してきた刑事が念押しするように確認してくる。鶴松は小さく肩をすぼめ、
「それはまあ、広中くんが勝手に勘違いをしているだけと思いますが、はい、そういう噂もある広中大夏くんです」
と、その刑事は言った。
「と、なると、あれですね。今回の五人の被害者のうち、半分以上の三人が、ヤマモトと関係がある人物、ということになりますね」
大会議室がざわりと揺れた。三枝が眉を顰めた。
「どういうことかね? 君、詳しく説明をしてくれたまえ」